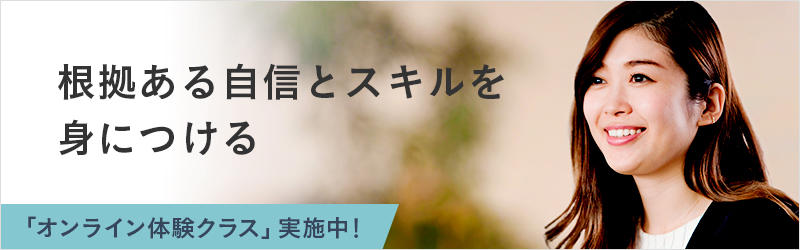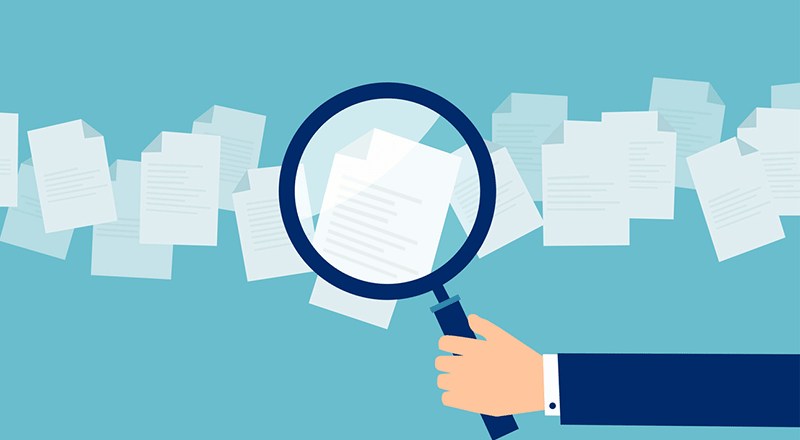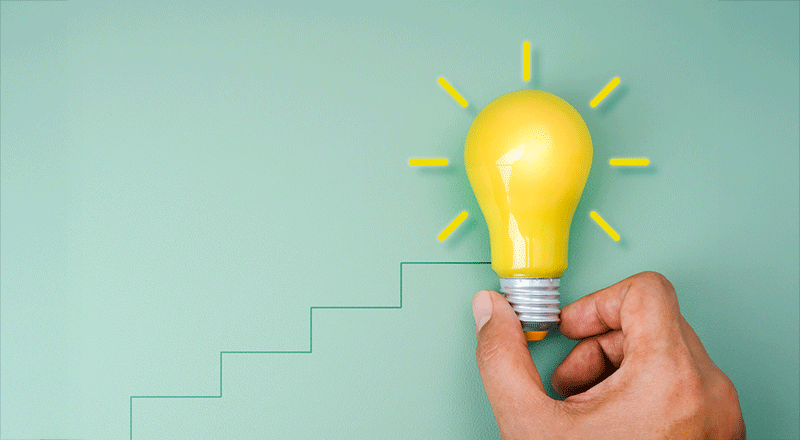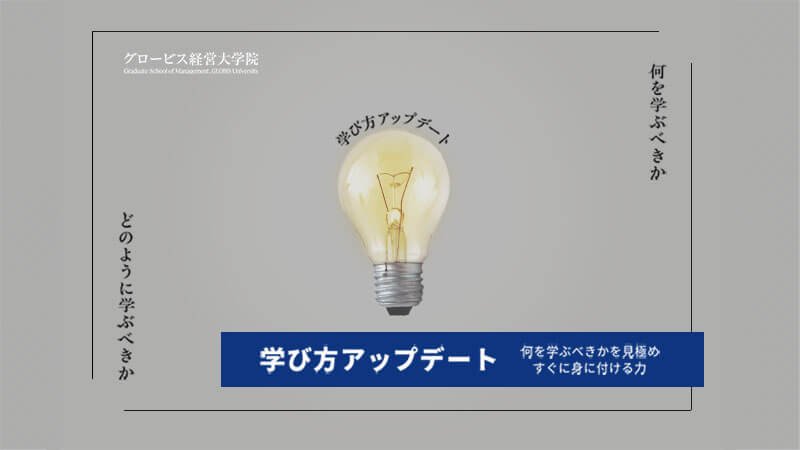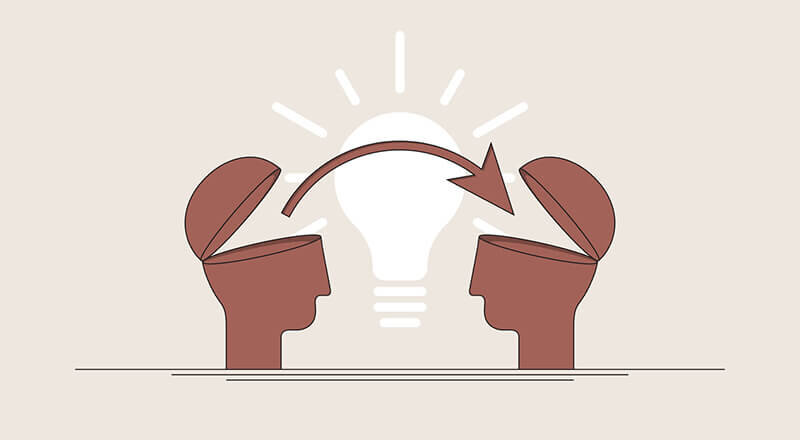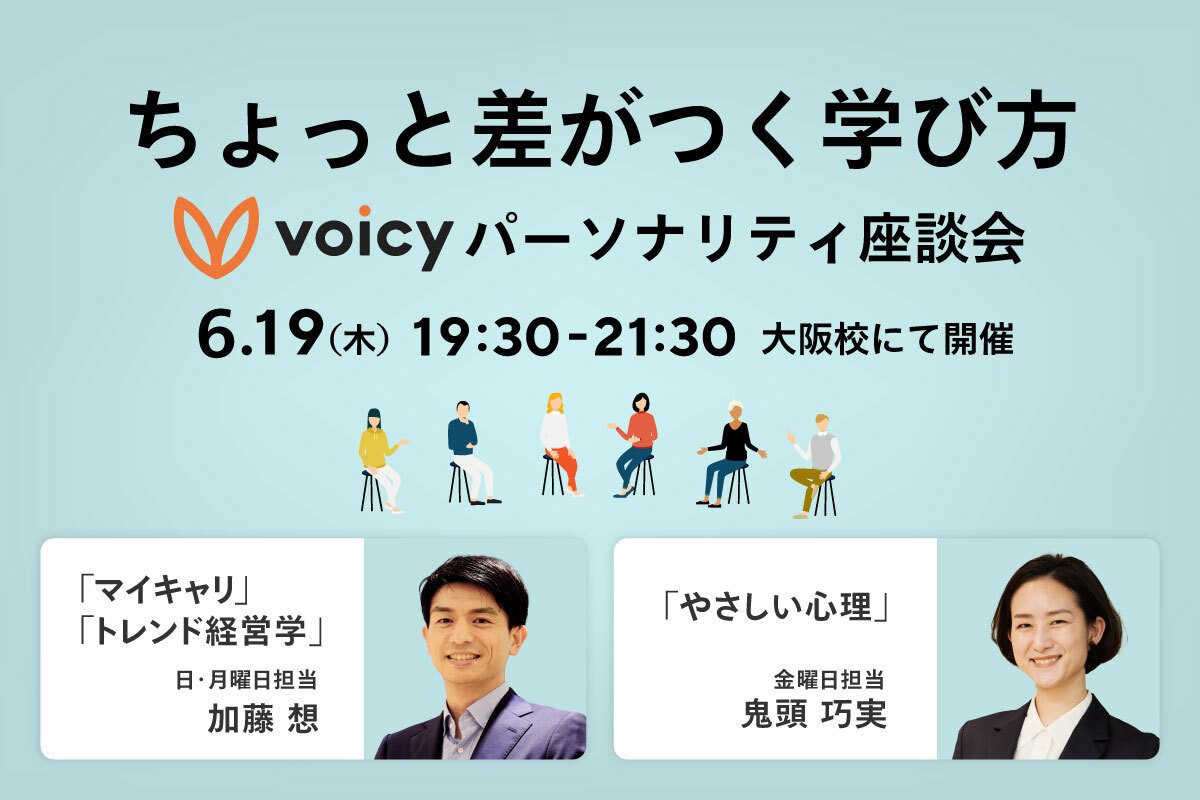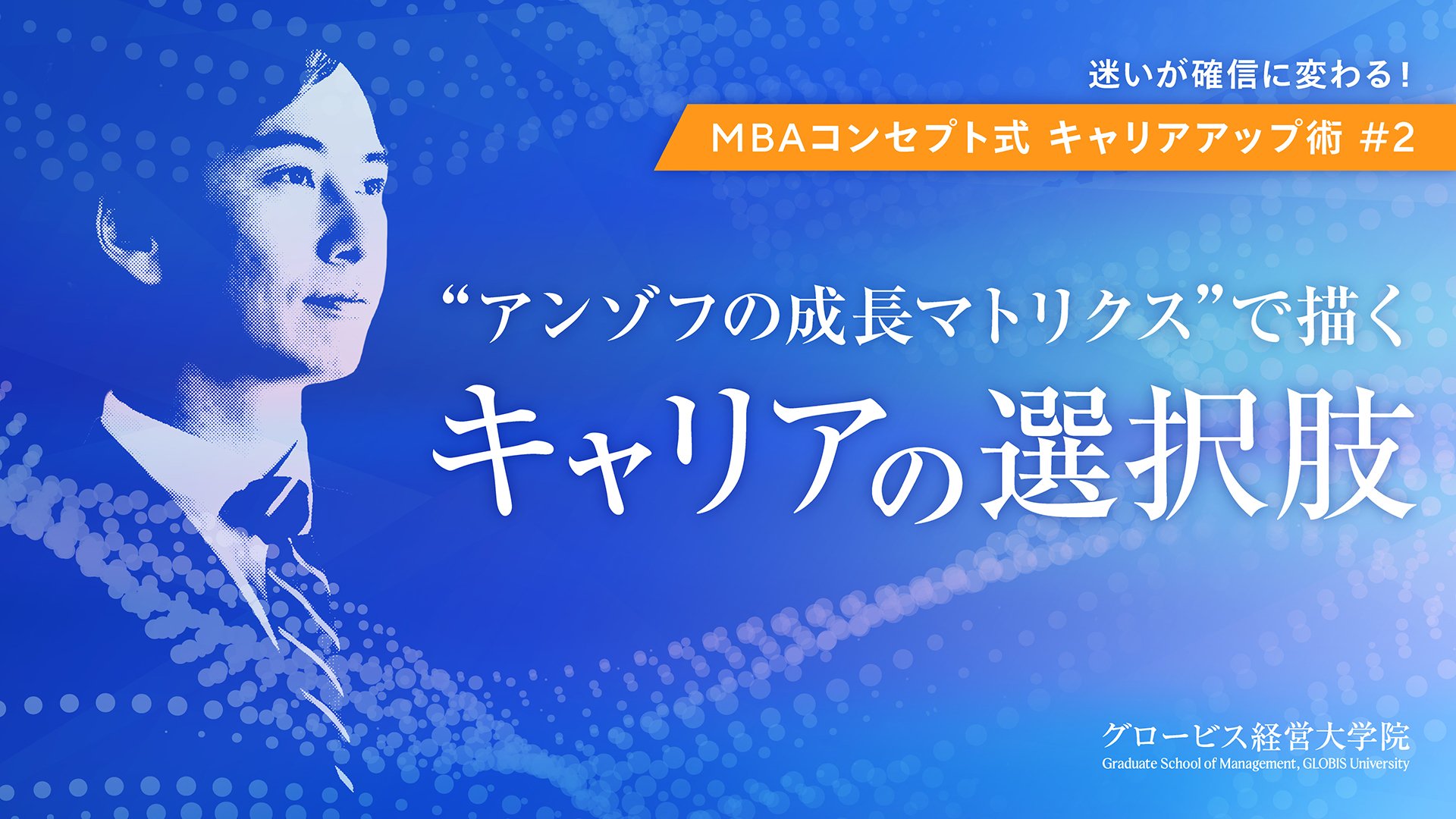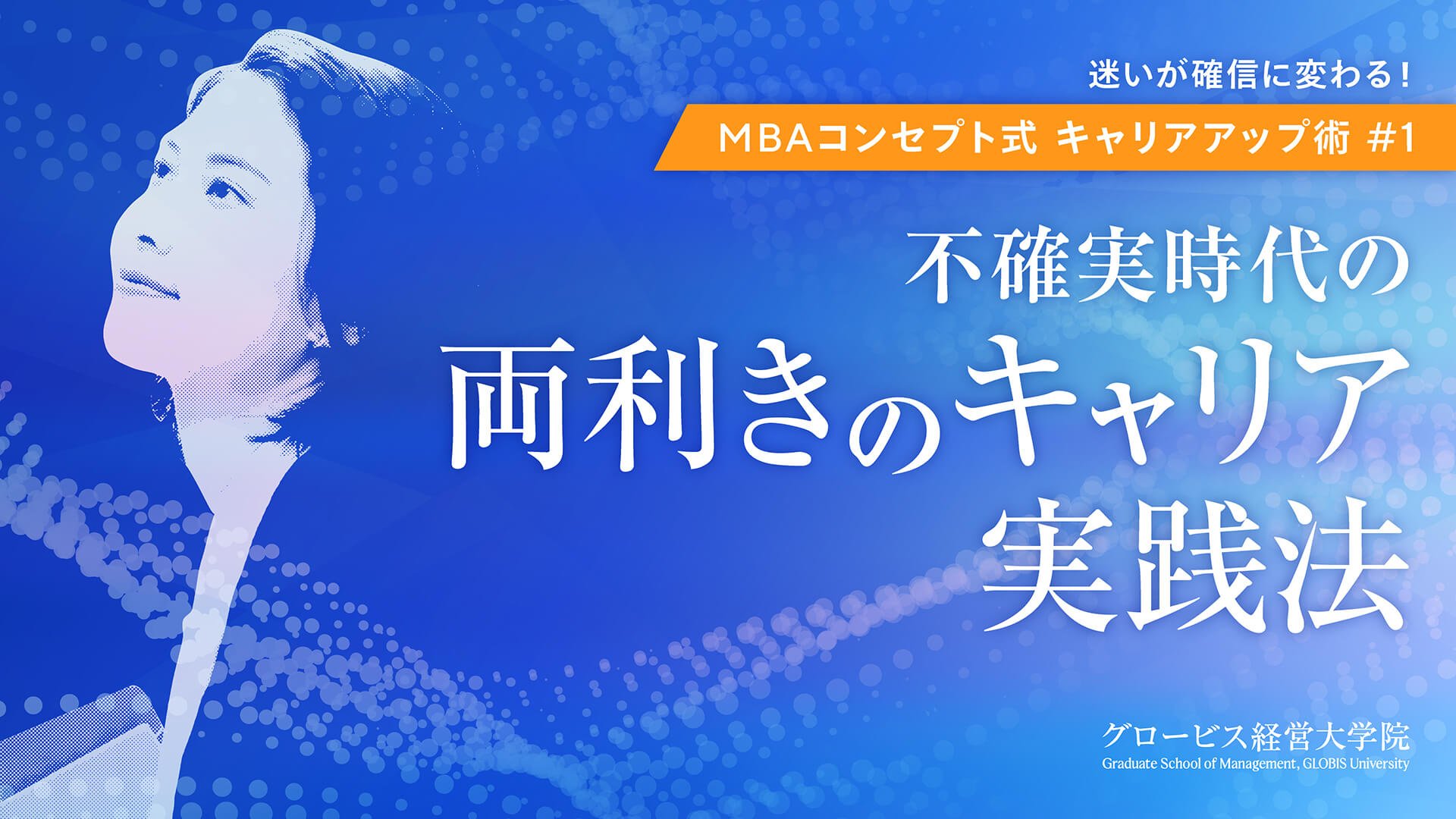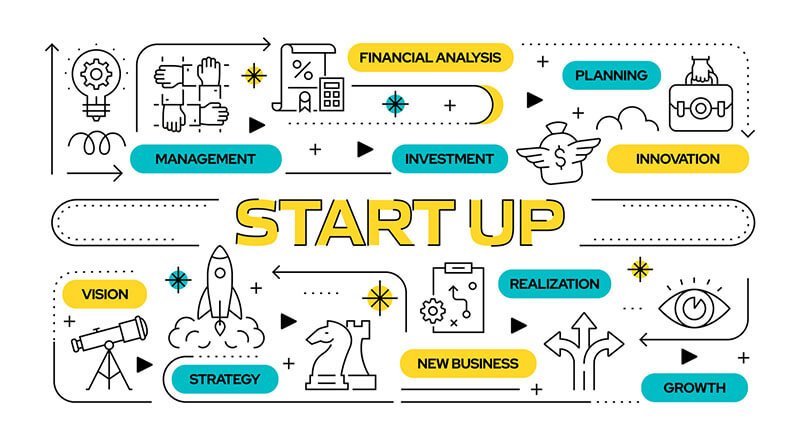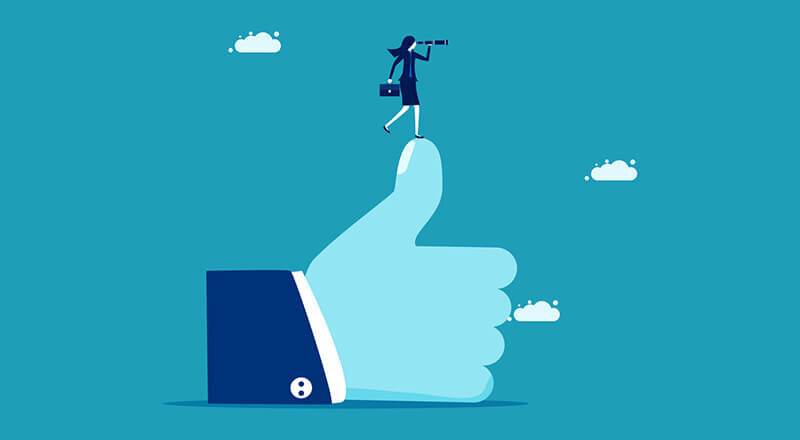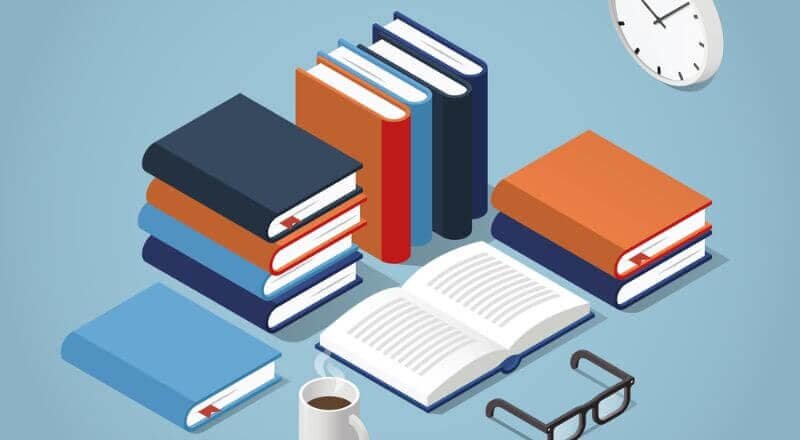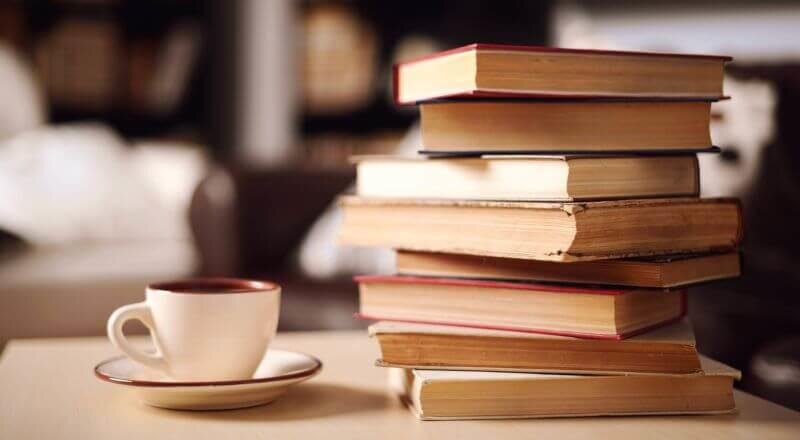
目次
コミュニケーションを円滑にするために、社会人が身に付けておきたいスキルのひとつである「語彙力」。
語彙力があると、話に広がりや深みが出ますし、何より自分の考えを的確に伝えることができます。
本記事では、語彙力を高めていくうえで、ぜひ日常的に取り入れていただきたいおすすめの方法を紹介します。
語彙力とは
語彙力とは、単語をどれだけ多く知っているか、そしてそれをどれだけ適切に使いこなせるかの能力です。つまり、ボキャブラリーの豊富さと、言葉を適切に使う力の両方を指します。
「語彙力が高い人=知っている言葉の数が多い人」とイメージされる方も多いですが、それだけでは不十分です。語彙力は、以下2つの能力で構成されており、「言葉をどれだけ知っているか」に加えて「適切に使えるかどうか」も意識する必要があります。
- ①語彙の量:どれだけ多くの言葉を知っているか
- ②語彙の質:状況に応じて、知っている言葉を適切に選び、使えるかどうか
語彙力がない人の5つの特徴
語彙力が不足している人には、共通する特徴があります。以下の項目にいくつか当てはまるようであれば、語彙力を意識して伸ばしていくことで、日々のコミュニケーションがぐっとスムーズになるかもしれません。
言いたいことが上手く伝えられない
語彙力がない人の最も顕著な特徴は、自分の考えや感情を適切に言語化できないことです。
頭の中では明確なイメージや考えを持っているにも関わらず、それを表現する適切な言葉が見つからず、「えーっと」「なんというか」といった言葉でつなぎながら話すことが多くなります。
また、同じ言葉を繰り返し使う傾向があり、「すごい」「やばい」「普通」といった漠然とした表現に頼りがちです。これでは、聞き手に具体的なイメージを伝えることが困難になります。
読んだことが理解できない
語彙力と読解力は密接に関係しています。知らない単語が多いと、文章全体の意味を正確に把握することができません。
特にビジネス文書や専門書を読む際、専門用語や抽象的な概念を表す言葉の意味が分からないと、内容の本質を理解することが困難になります。
その結果、重要な情報を見落としたり、誤った解釈をしてしまったりするリスクが高まります。読書においても、表面的な理解にとどまり、深い洞察を得ることができなくなります。
物事を深く考えられない
思考は言葉によって行われるため、語彙力が不足していると思考の幅と深さが制限されます。
複雑な概念や微細な違いを表現する言葉を知らないと、物事を単純化して捉えがちになります。例えば、「好き」と「嫌い」の二極化した思考になりやすく、「やや好き」「どちらかといえば嫌い」といった細かなニュアンスを表現できません。
このような状況では、問題解決においても多角的な視点を持つことが困難になり、創造的で柔軟な思考を展開することができなくなります。
感情のコントロールができない
感情を適切に言語化できないことは、感情のコントロールにも悪影響を与えます。
自分の感情を具体的に表現する語彙が不足していると、「イライラする」「嫌だ」といった漠然とした感情表現しかできません。しかし、実際の感情はもっと複雑で、「失望している」「不安を感じている」「困惑している」など、より具体的な言葉で表現できるはずです。
適切な言葉で感情を表現できると、自分の気持ちを客観視でき、感情をコントロールしやすくなります。逆に語彙力が不足していると、感情が混乱したまま適切に処理できず、ストレスを抱えやすくなります。
言葉遣いが間違っている
語彙力がない人は、言葉の正確な意味や使い方を理解していないため、不適切な場面で間違った言葉を使ってしまいます。
例えば、敬語の使い方が不正確だったり、ビジネスシーンで使うべき言葉とカジュアルな言葉を混同したりすることがあります。また、言葉の持つニュアンスを理解していないため、相手に誤解を与えたり、不快感を与えたりするリスクもあります。
特にビジネスの場面では、適切な言葉遣いができないことで、プロフェッショナルとしての信頼性を失う可能性もあります。
語彙力が低いことによる3つのデメリット
それでは、語彙力が低いと具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。
伝える力や表現力が弱くなる
誰かと会話をする中で「いまいち相手に伝わっている気がしない...」など、自分の意見やイメージを相手にうまく伝えることができません。
語彙力がある人は、類義語や言い換えの言葉をたくさん知っているので、話の内容や相手に合わせて適切な言葉や表現を選ぶことができますが。
しかし、語彙力が不足していると、ごく限られた言葉しか使うことができないため、自分の伝えたいことをうまく表現できなくなります。
理解力や読解力が低くなる
語彙力が低いと、相手の話を理解する力や読解力の低下にもつながります。
言葉の意味自体を知らなかったり、ちょっとした言葉のニュアンスを理解できなかったりするため、表面的にしか内容を捉えることができなくなります。
思考が浅いものになる
人間は、頭の中にある「言葉」を使いながら物事を考えます。
そのため、知っている言葉の数や使いこなせる言葉の数が多いほど、思考は広く、深いものになります。
逆にいえば、語彙力が低いと、それだけ「多面的に物事を捉える力」が弱く、思考が浅いものになってしまうということになります。
語彙力を高める4つの方法
語彙力は、日々の心がけや努力の積み重ねによって鍛えられていきます。
おすすめの方法を4つほど紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
言葉への感度を高める
一番大事なのは、日常的に「言葉への感度を高める」ことです。
「言葉にこだわる」と言ってもよいかもしれません。
例えば、私たちは一日の中で、ニュース記事を読んだり、誰かと会話したり、ドラマや映画を観たりなど、たくさんの言葉に触れます。
そこで使われている言葉をなんとなく聞き流すのではなく、「どのような言葉が、どのような場面で、どのように使われているか」を意識するようにしてみてください。
そして、「素敵だな」と感じる表現があればメモしたり、知らない言葉が出てきたらすぐに調べたりする習慣をつけるようにしましょう。
さまざまなジャンルの書籍を読む
当たり前ですが、書籍にはたくさんの言葉が使われています。
そのため、読書習慣を持つことも語彙力を高めるうえで非常に有効です。
ここでのポイントは、多様なジャンルの本を読むことです。
特定の分野に偏ると、そこで使われる語彙に詳しくなってきた時に、新たに出会える語彙量が減ってしまうからです。
例えば普段「ビジネス書ばかり読んでいる」という人は、現代小説や古典文学、エッセイ、科学書、哲学書などのジャンルの本も意識的に手に取るようにしてみてください。
多様な人と会話する
よく使われる単語や言葉の表現方法は、属しているコミュニティなどによって、影響を受けることが多いです。
そのため、自分とは異なる世代や性別、職業、価値観、ライフスタイル、趣味嗜好の人と話してみるという方法もおすすめです。
相手との会話の中で「面白い」「素敵だ」と感じる言葉の言い回しや表現を、自分の会話の中で取り入れていくことで、自分自身の世界も広がりますし、語彙のレパートリーもぐんと増えます。
アウトプットする
インプットだけでなく、「書く」「話す」といったアウトプットも重要です。
アウトプットの手段は、言葉を使うならなんでもかまいません。
- SNSやブログで発信する
- 日記をつける
- 動画や音声メディアを活用する
など、現代は日常会話はもちろん、個人が情報を発信できる手段がたくさんあります。
そうした場を上手く活用しながら、自分の考えや意見などをアウトプットする習慣を持つようにしてみてください。
このときに重要なのが、抽象的な言葉や指示語、形容詞をなるべく避けて、「よりよい表現はないか」と推敲を重ねることです。
「他者に読まれている」という感覚が適度なプレッシャーになるため、自然と正しい言葉を使うことを意識したり、もっと良い表現がないか調べるようになります。
仕事に効く「伝える力」を実践的に鍛える
語彙力は、"自分の考えを言語化する力"の土台です。ただ言葉を知っているだけでなく、ただ言葉を知っているだけではなく、「どの言葉を、どう伝えるか」が問われるビジネスの現場では、語彙力はコミュニケーション力の核となる要素のひとつです。
グロービスでは、この力を"知識"ではなく"実践"を通じて身につけていきます。具体的には、以下のような科目を通じて、論理的に考え、説得力をもって伝える力を磨いていきます。
クリティカル・シンキング
激変する環境下でも成果を出し続けるために必要な、論理的に考え、伝える力を鍛える科目です。問題解決力・意思決定力とともに、「筋道立てて話す」「わかりやすく説明する」力が磨かれ、日常の発言や説明に説得力が生まれていきます。
ファシリテーション&ネゴシエーション
合意形成や交渉の現場で必要な、ファシリテーター、ネゴシエーターの実践的な考え方やスキルを学びます。相手の立場をくみ取りつつ、適切な言葉で場を進めていく力は、実践演習を通じて体得。語彙だけでなく、相手の納得を引き出す"伝え方"が磨かれます。
ビジネス・プレゼンテーション
伝えるだけでなく、人や組織を「動かす」ための表現力を鍛えます。資料づくりから実演まで徹底的に行う演習を通じて、場面や聴き手に応じた言葉の選び方・語彙の幅・表現力が大きく向上します。
グロービスの学びを通じて、語彙力を含むビジネスコミュニケーション力を高めていきませんか?
まずは体験クラスに参加して、実際の授業の雰囲気を体感してみてください。
▼体験クラス&説明会(無料)のお申し込みはこちら
まとめ
言葉は、私たちのコミュニケーションを支える重要な要素であり、私たちの世界を広げてくれるツールです。
日本語という言語は、本当に豊かな言語で、使える語彙数が多いほど、心の機微や微妙なニュアンスも的確に伝えることができますし、理解することもできます。
ぜひ今回ご紹介した方法を日常で意識して取り入れ、語彙力を高めていってください。
オンライン体験クラス&説明会日程
著者情報

村尾 佳子(グロービス経営大学院 経営研究科 副研究科長)
関西学院大学社会学部卒業。大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策修士。高知工科大学大学院工学研究科博士(学術)。大手旅行会社にて勤務後、総合人材サービス会社にてプロジェクトマネジメント、企業合併時の業務統合全般を経験。現在はグロービス経営大学院にて、事業戦略、マーケティング戦略立案全般に携わる。教員としては、マーケティング・経営戦略基礎、リーダーシップ開発と倫理・価値観、経営道場などのクラスを担当する。共著に『キャリアをつくる技術と戦略』、27歳からのMBAシリーズ『ビジネス基礎力10』『ビジネス勉強力』『リーダー基礎力10』がある。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。