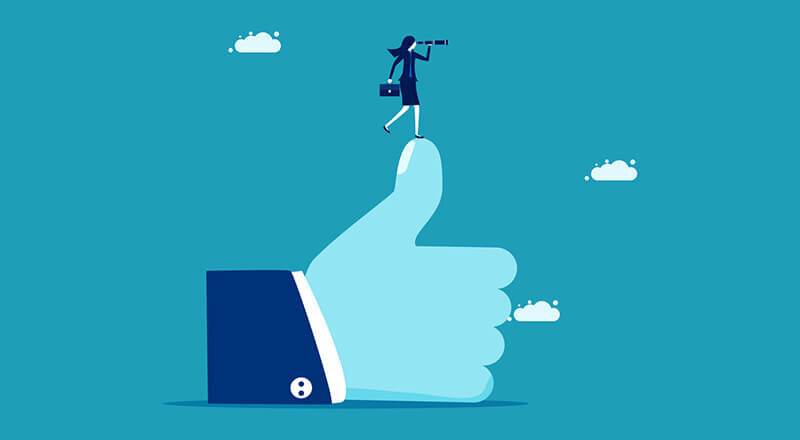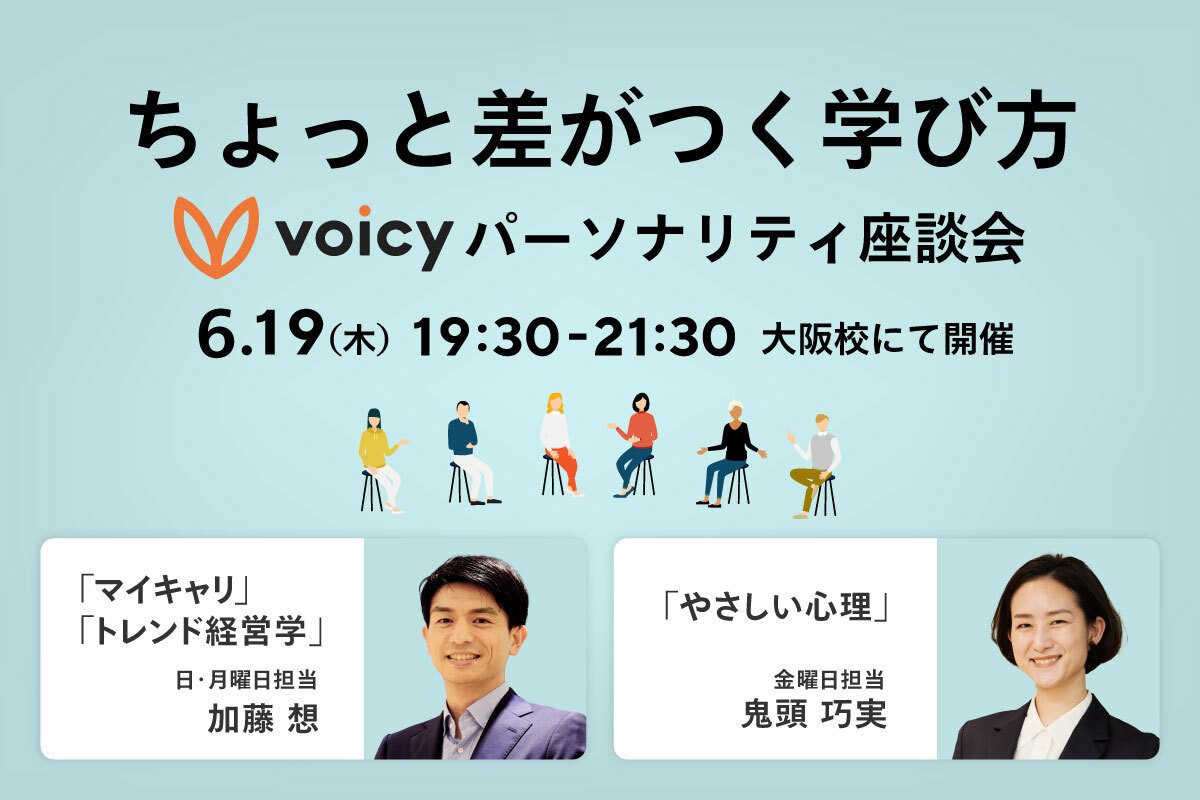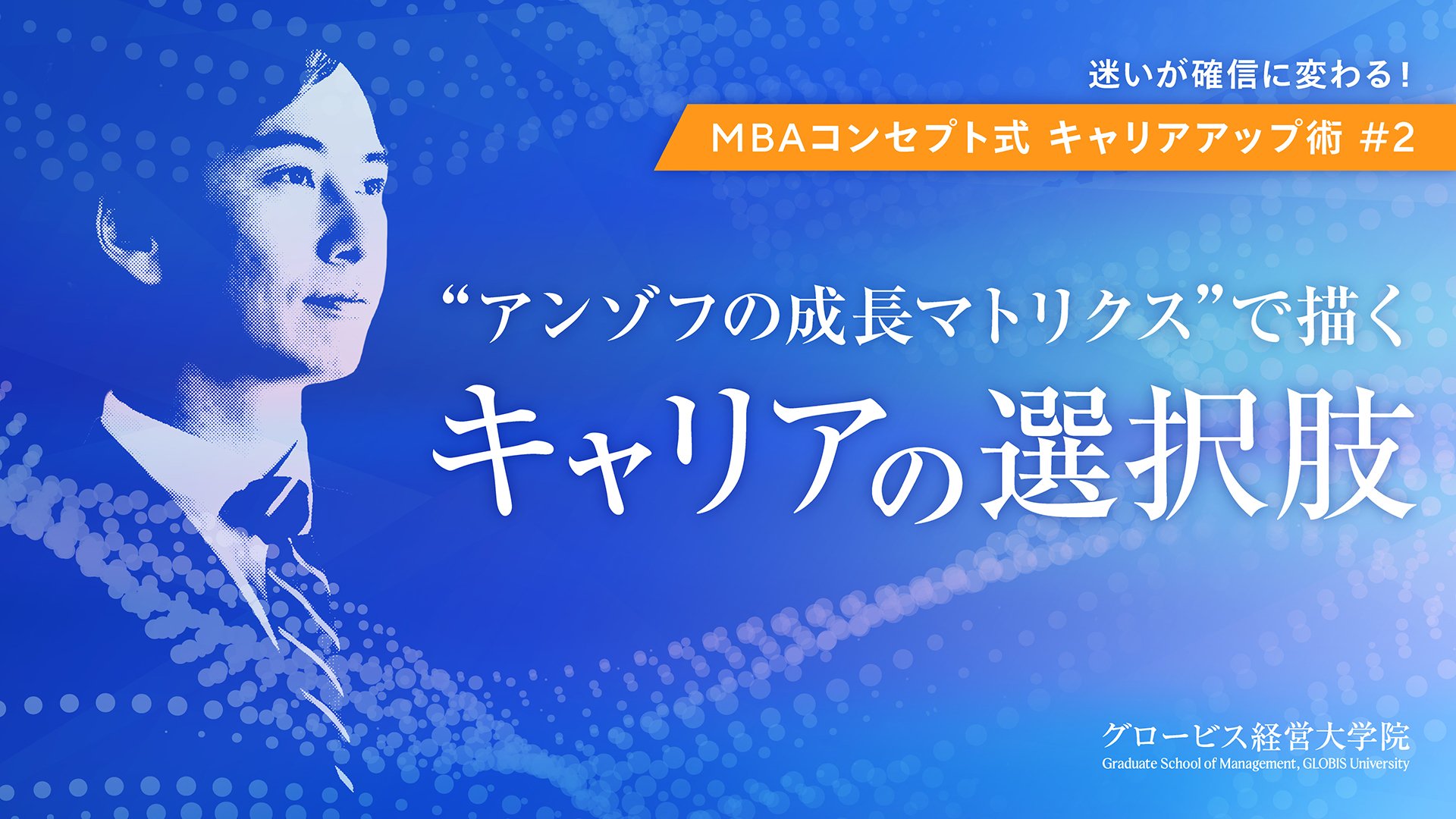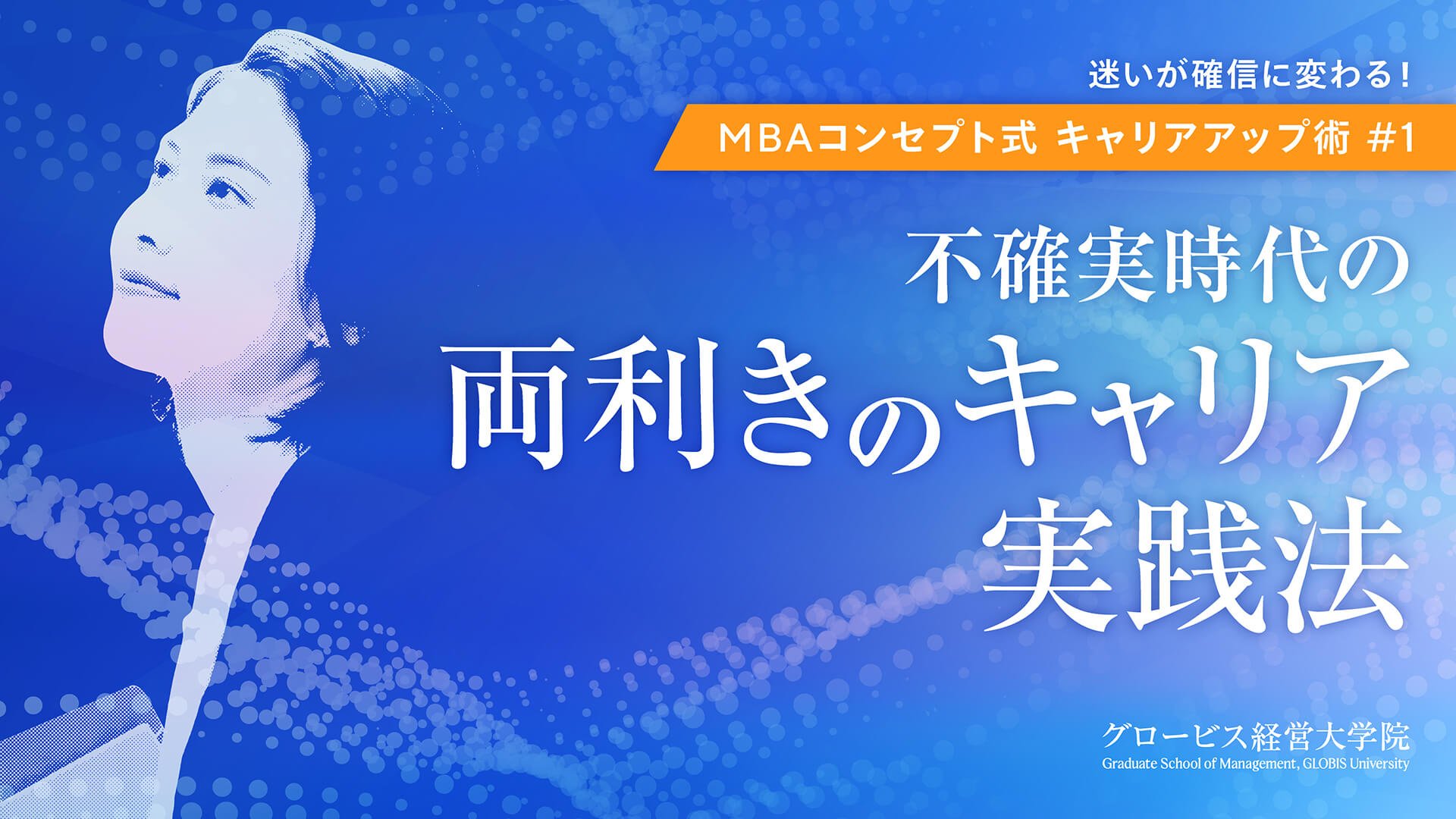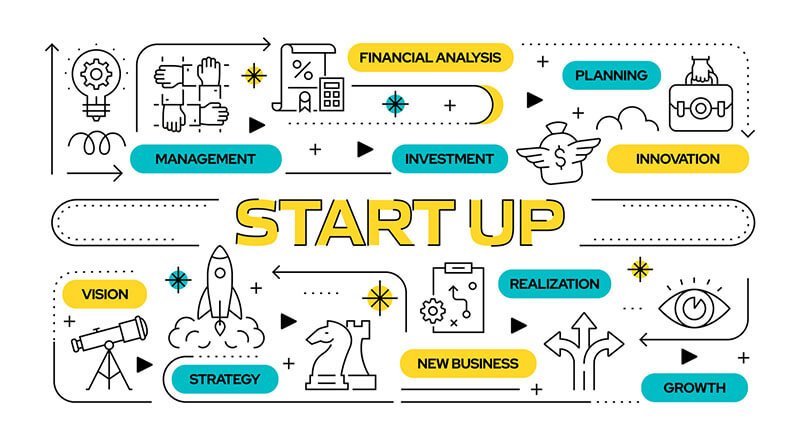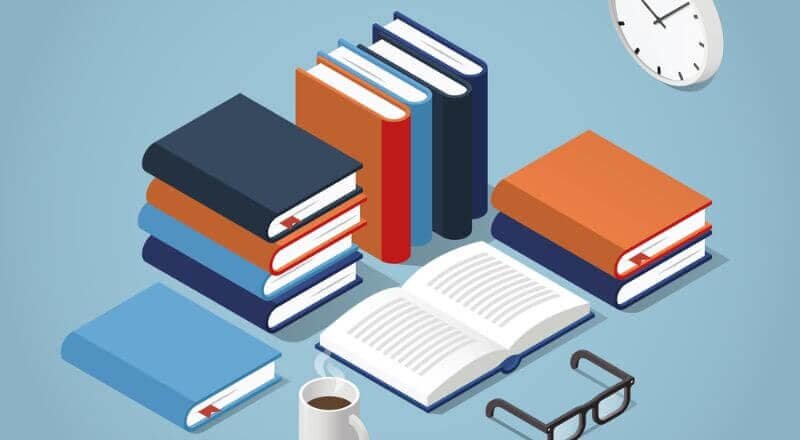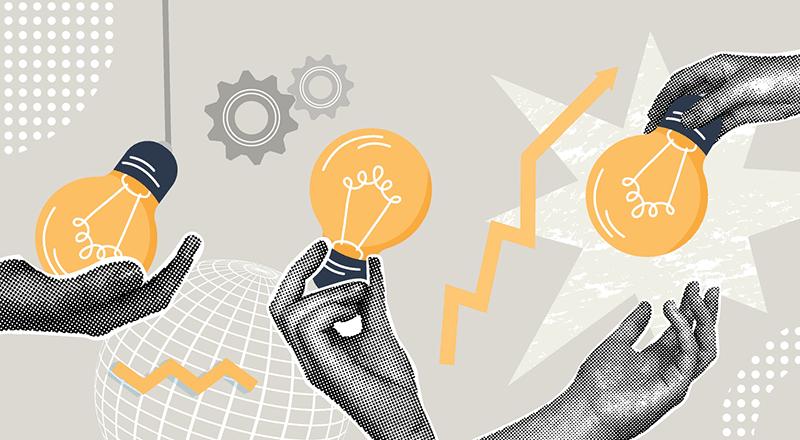
目次
「仕事ができる人」と聞いて、あなたはどんな人を思い浮かべますか?スキルや知識の豊富さを挙げる人が多いかもしれませんが、それだけでは測れない"違い"があることに気づく場面もあるはずです。今回は、仕事の成果を左右する「センス」とは何か、そしてその磨き方について考えていきます。
センスとは「文脈を読む力」
同じ会議で同じデータを見ていても、ある人は数字の説明に終始し、ある人は背景や未来の展望まで踏まえて的確な発言をする――この差を生むのが、センスです。ここで言うセンスとは、「文脈の中で適切な判断や振る舞いができる力」と言い換えることができます。これは、単なる知識やスキルでは補いきれない領域です。
センスは"生まれつき"ではなく鍛えられる
センスというと「持って生まれた才能」と捉えがちですが、そうではありません。たとえば、"モテる人"を想像してみてください。「LINEの返信は3時間あける」や「初デートは聞き役に徹する」などのテクニックだけでは、人の心は動きません。モテる人は、小手先の技術ではなく、日々相手の反応を観察し、何が求められているのかを感じ取る力を磨いているのです。
仕事におけるセンスも同じです。知識やマニュアルではなく、場面に応じた最適な言動を積み重ねることで、少しずつ体得していくものです。つまり、センスは後天的に身につけられる力なのです。
センスを磨くための3ステップ
センスを磨くには、次の3つの行動が効果的です。
①観察する:「あの人の発言はなぜ説得力があるのか」など、周囲の言動を意識的に見る。
②仮説を立てる:「結論のあとに具体例を挙げるから響くのかも」など、自分なりの理解を深める。
③実行・検証する:実際に試し、うまくいった・いかなかった理由を分析し、次に活かす。
このプロセスを繰り返すことで、的外れではない発言や行動が徐々にできるようになり、自然とセンスが身についていきます。
スキルとセンスは別物と考える
最後に意識したいのが、スキルとセンスは別物だという考え方です。スキルには正解がありますが、センスには明確な答えがなく、その場その場の文脈や空気感によって求められるものが変わります。
そのため、センスを磨くには"正解"を求めすぎず、「トライアンドエラーを重ねる姿勢」が重要です。完璧を目指すのではなく、その場に合った最適解を見つけようとする行動こそが、センスを磨くことにつながるのです。
著者情報

加藤 想(グロービス経営大学院 大阪校企画営業責任者)
神戸大学工学部卒業、同大学院工学研究科修士課程(工学)修了。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。大手通信会社にて設備設計業務、採用活動に従事した後、サービス戦略部門にて新サービスの立案、AI、BPRなどを担当。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院の学生募集企画にて学生のキャリア相談、新規施策立案などを行っている。また、グロービス経営大学院のVoicy「ちょっと差がつくビジネスサプリ」のパーソナリティを務める。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。