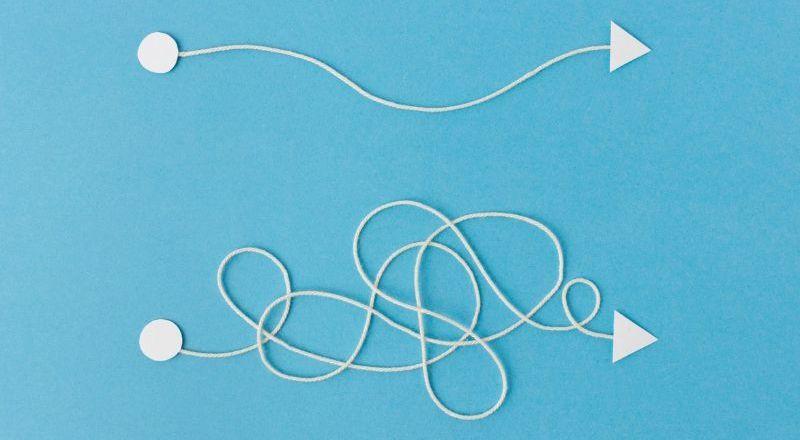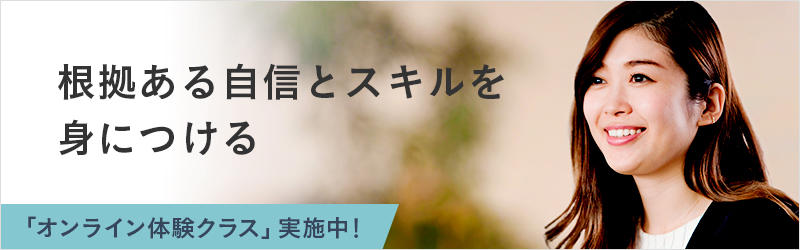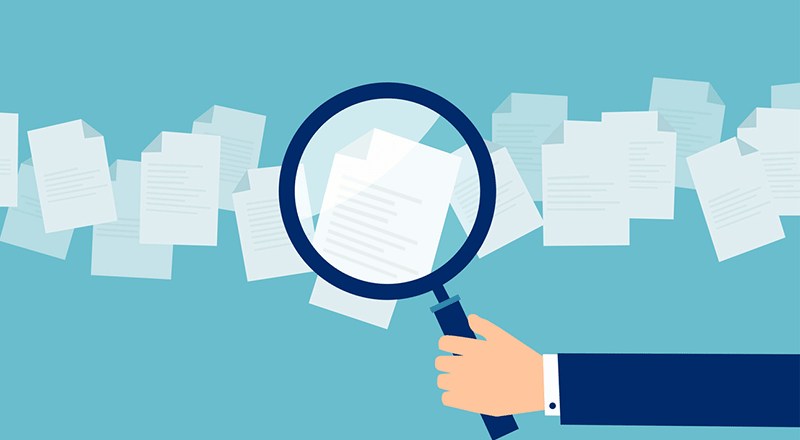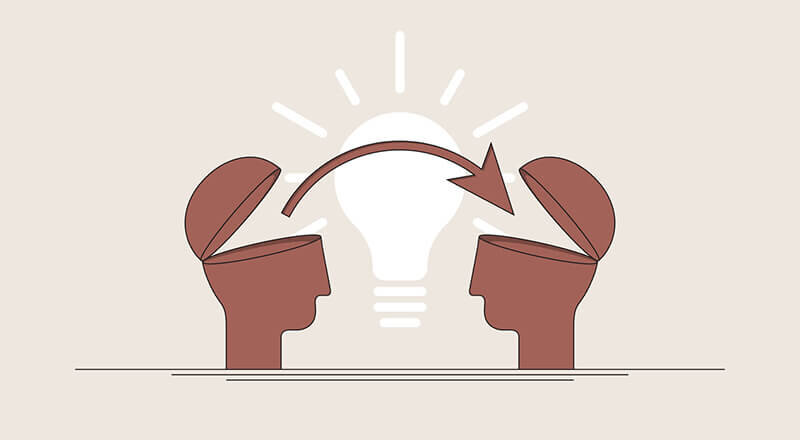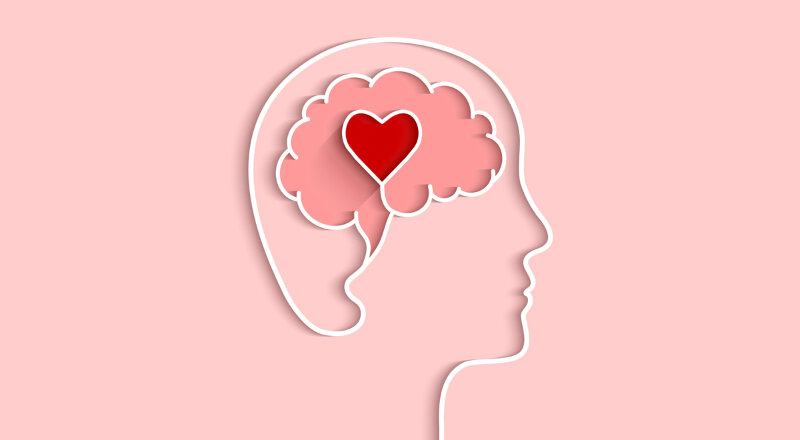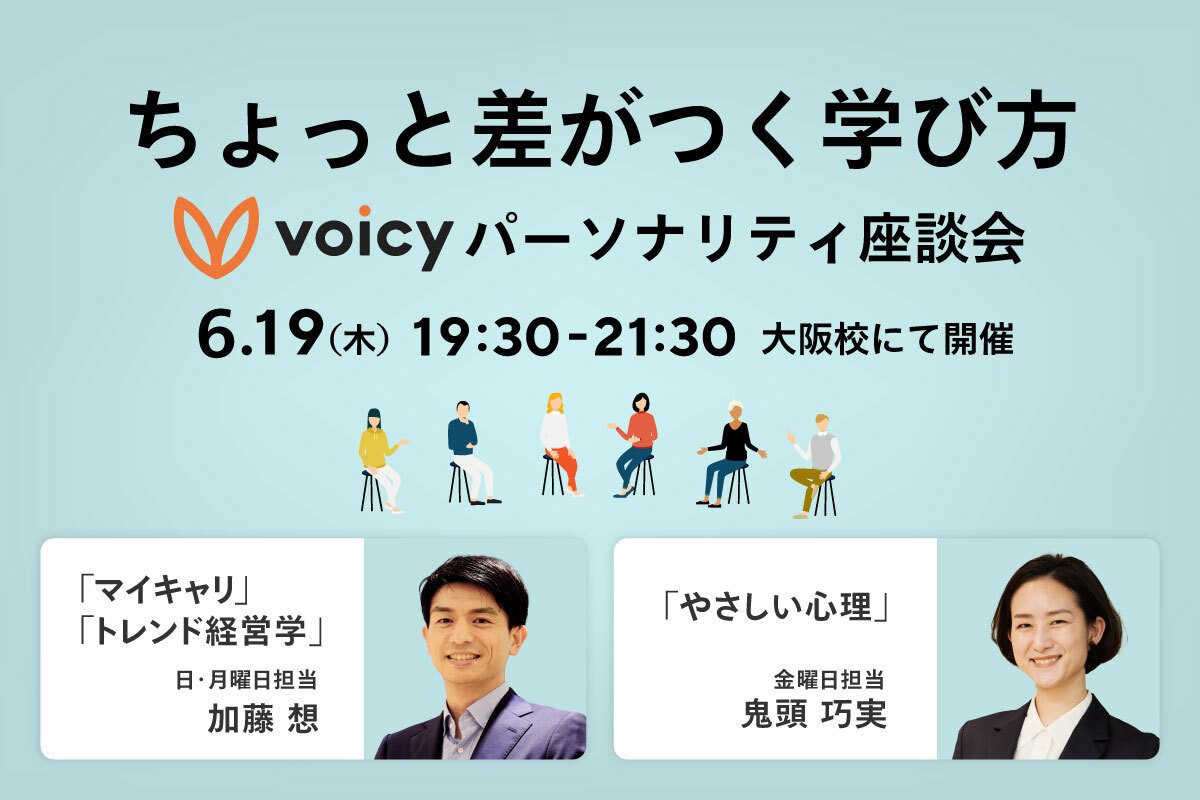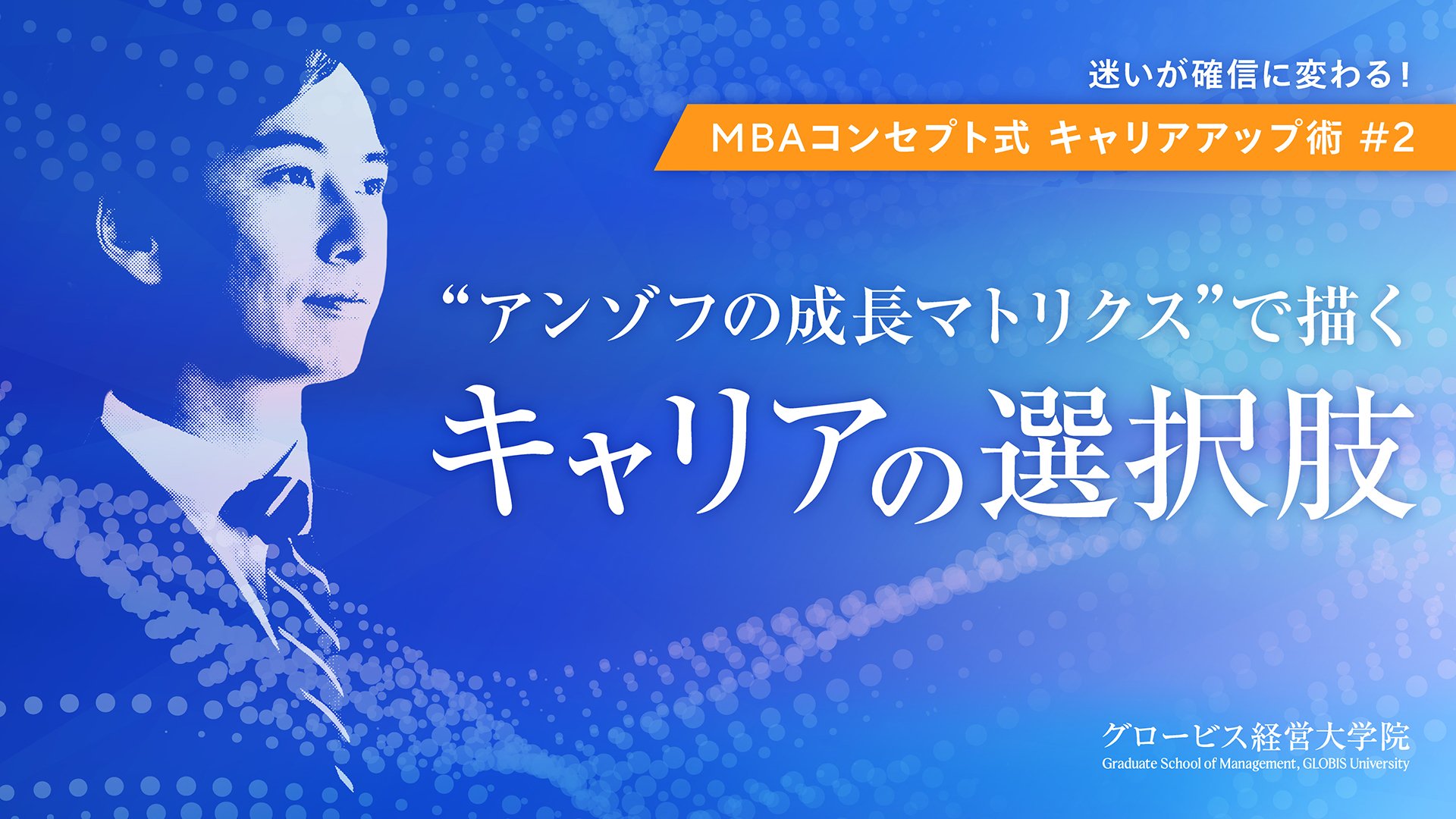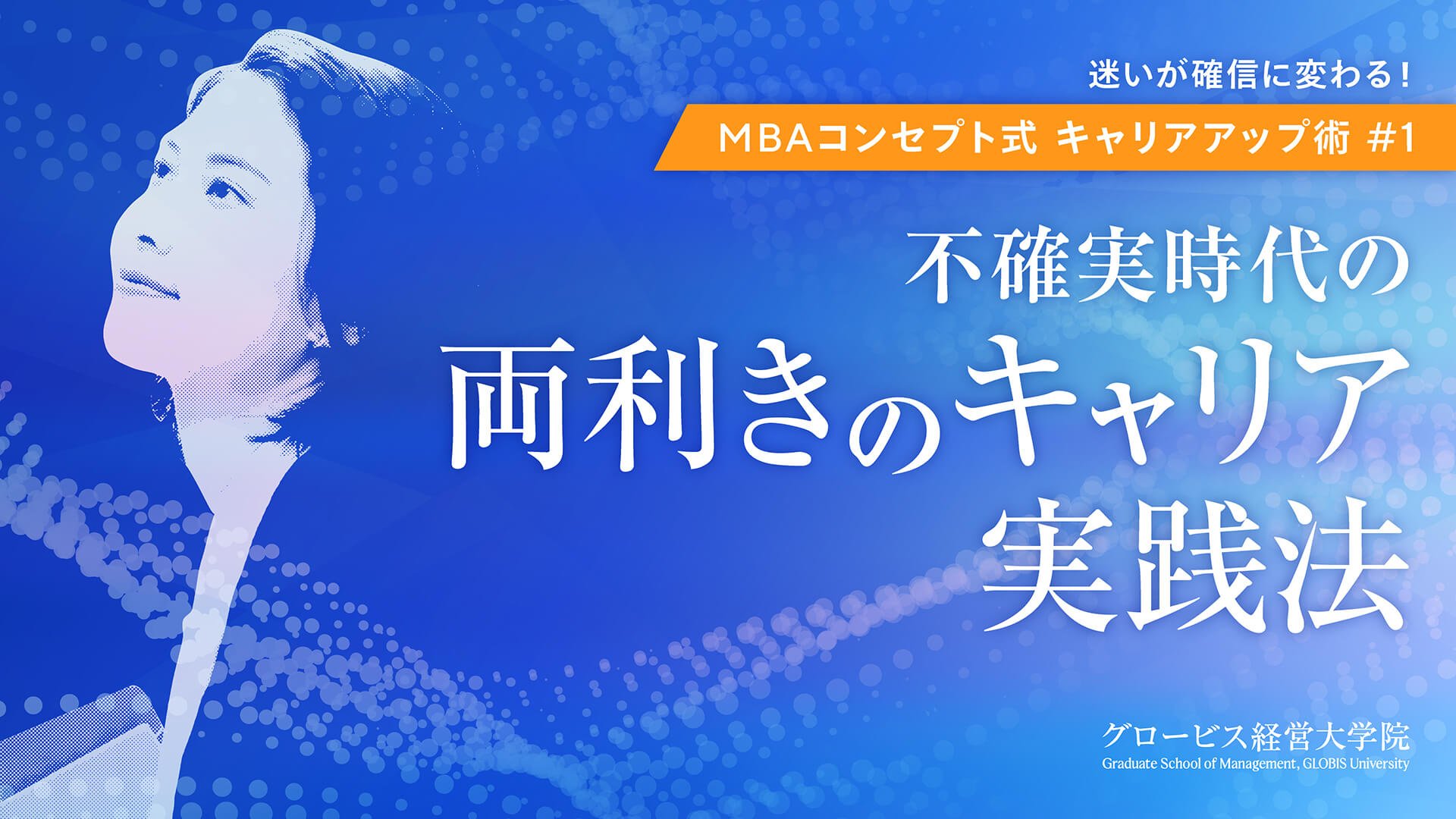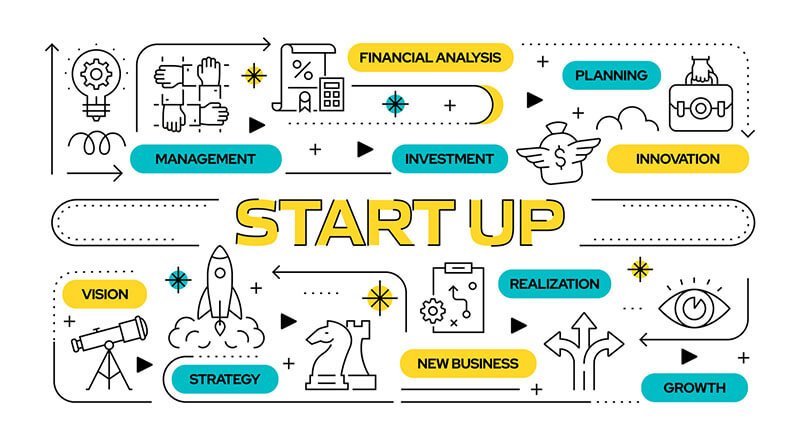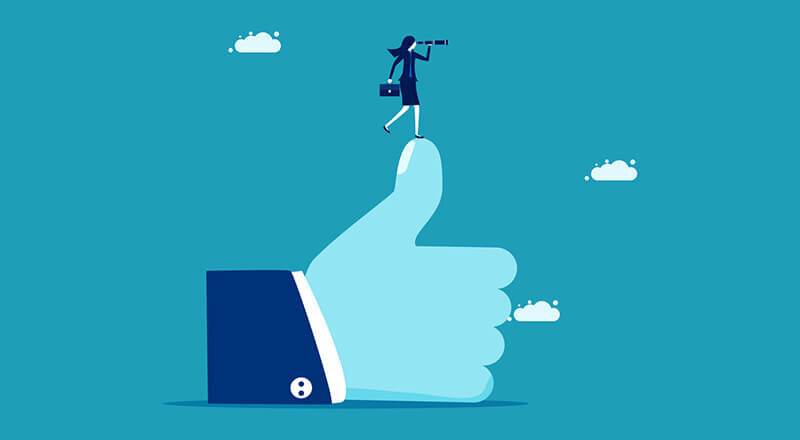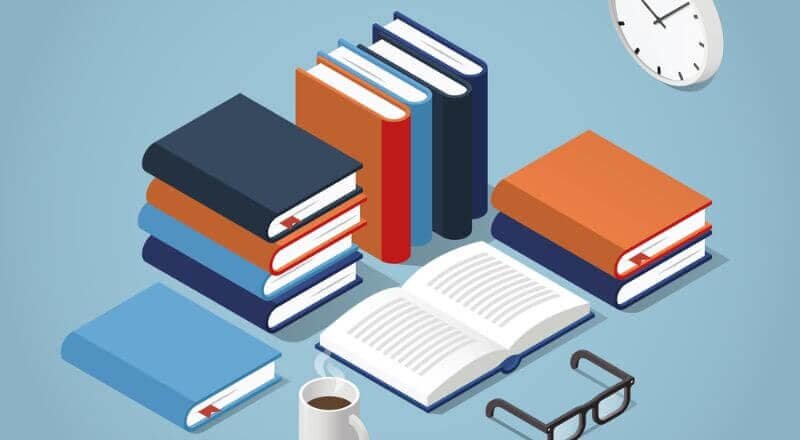目次
「上司や先輩、同僚となぜか話がかみ合わない...」
「自分の話したことが上手く伝わっていない...」
など、コミュニケーションの中で相手とのズレを感じることはありませんか?
本記事では、話がかみ合わないときの要因や対処法についてご紹介します。
なぜ「話がかみ合わない状態」が起こるのか?
まずは、話がかみ合わない原因について考えていきましょう。
例えば、「ほぼ全員と話がかみ合わないと感じる」という場合は、自分自身に問題がある可能性が高いです。
「ほかの人とは問題ないけど、特定の人とは全くかみ合わない」という場合は、自分だけでなく相手にも問題があるかもしれません。
私自身も前職の会社に入社したばかりの頃、教育担当の先輩とかみ合わないことに悩んでいました。
入社して日が浅く、ほかの人と話すこともあまりなかったので「自分はこの会社と合わないかもしれない」と思っていたんです。
しかし、上手くコミュニケーションが取れないのは特定の相手だけということに気付いたときには、とても安心しました。
ほとんどの場合、どちらか一方だけに問題があるのではなく、複数の要因が絡んでいます。
また、「仕事の話題はいいけど、プライベートの話やちょっとした雑談が苦手...」という人もいるかもしれません。
今回はビジネスにフォーカスした「話がかみ合わない要因」を見ていきましょう。
話がかみ合わない原因
代表的な原因を5つ紹介します。
話の内容が漠然としている
相手との認識にズレが生じる要因として、「話の内容がぼんやりしている」「主語や述語のないあいまいな会話になっている」などが挙げられます。
話の抽象度が高いということは、そのぶん解釈の余地が大きいということです。
情報が足りない部分は相手が想像で補っているため、受け取り方や解釈の仕方によってズレが生じてしまいます。
相手が推測しなくても内容が理解できるように、具体的に伝えることが大切です。
前提条件にズレがある
そもそもの前提や目的の共通認識が取れていないと、話がどんどん違う方向に進んでしまいます。
例えばビジネスの場であれば、話を始める前に、議論のゴールや目的、前提条件などを確認しましょう。
好む話の組み立て方が異なる
人によって好みの話し方が異なるため、事前におさえておくことが重要です。
例えば、結論から話してほしい人もいれば、順を追って説明してほしい人もいます。
相手のコミュニケーションの好みを知ることで、お互いにイライラしてしまう...という状況を避けることができるでしょう。
主題に関する知識量に差がある
持っている情報量や知識量に大きなギャップがある場合も、相手との会話が成り立たないことが多いです。
例えば、新入社員と部長が話すための会議や、「若手から提案を」と人事が設定したミーティングなど。
そういった場で、既存社員と新入社員の話が全くかみ合わず、以降それらの機会が設けられることはなくなった...なんてことも。
会社や商材、サービスに対する知識量の差から、既存社員と新入社員との間にギャップが生じ、こういったことが起こってしまうのです。
頭の中で整理されていない
頭の中を整理せず、思いついたことをそのまま伝えてしまうと、お互いの理解が浅いところで留まってしまいます。
また、こうしたケースは、話し手だけでなく、受け手の頭の中が散らかっている場合にも起こり得ます。
議論や会話を進める中で、「そもそもの目的はこれとこれです」「つまり、こういうことですか?」「今の話で出た結論はこうですよね」と整理することが大切です。
話がかみ合わない時の対処法
「なかなか話がかみ合わない」と感じたとき、どのように対処すればよいのでしょうか。
おすすめの方法を5つ紹介します。
話の前提条件を合わせる
「そもそもの前提条件はなにか」「どこで話がズレたのか」と再度認識のすり合わせを行いましょう。
「私はこういう認識で話していましたが、合っていますか?」と相手に確認しながら、話を進めることが大切です。
主語・述語を明確にする
「誰が」「何をするのか」といった主語・述語があいまいなまま会話を進めると、認識違いが生じてしまいます。
とくに、急いでいるときや時間がないときほど、言葉を省略してしまうことが多いです。
仕事の大切な話であれば、「先ほどのお話はこういうことでしたよね」と確認用のメモを送ってみるのもよいでしょう。
相手の理解度を確認する
「相手がどこまで理解しているか」「どこから認識がズレているか」を確認することも重要なポイントです。
例えば、自分が上司の立場で部下と話をする際は、「理解できたところまで話してみて」といった形で確認するのもよいでしょう。
自分が部下の立場で上司と話をする際は、事前にメモをつくった上で話したり、「こういった認識で合っていますか?」と確認したりすることが大切です。
後日仕切り直しをする
あまりにも相手と話がかみ合わない場合は、日を改めるというのもひとつの手です。
話している内容の重要度や優先度にもよりますが、「一度この話は持ち帰ってもいいですか」と打診してみましょう。
相手の意見を自分なりに整理したり、伝えるべきポイントをメモにまとめたりといった十分な準備を行い、後日仕切り直しすることをおすすめします。
頭の中を整理して伝える力を鍛える
言語化は、頭の中のことを、相手が理解しやすいよう整理し、まとめ、分かりやすい言葉で伝えるという一連のプロセスです。
当たり前ですが、そもそもの頭の中が散らかっていては、その後のプロセスも上手くいきません。
自身の思考を整理していく力が求められますが、ここで有効なのが「論理的思考」です。
論理的思考は、「複雑なものをシンプルにしていく思考法」です。
正しい論理構造の組み立て方や、因果関係の捉え方も身に着けることができるので、相手が理解しやすいのみならず、納得性のある伝え方もできるようになります。
上手く意思疎通がとれる人が実践していること
では、相手と上手く意思疎通ができる人は、どんなことを行っているのでしょうか。例えば、下記のようなポイントを実践している人が多いです。
- 会話内容だけでなく、表情なども含めて相手のことを理解しようとしている
- 相手の話をよく聞いて、自分の理解度を常に意識している
- 抽象度の高い言葉を避けたり、的確な言葉を選んだりしている
- 相手がどのように受け取っているのか、確認しながら話している
- 相手が伝えたいことや意図を汲み、共通認識が取れる言葉に置き換えている
重要なのは、自分が伝えたいことを一方的に押し付けるのではなく、相手に合わせてコミュニケーションを取るということです。
上記のポイントを意識して行動することが、意思疎通をスムーズにする第一歩となるでしょう。
分かりやすく話すには、論理的思考の習得がおすすめ
言語化は、頭の中のことを、相手が理解しやすいよう整理し、まとめ、分かりやすい言葉で伝えるという一連のプロセスです。
当たり前ですが、そもそもの頭の中が散らかっていては、その後のプロセスも上手くいきません。
自身の思考を整理していく力が求められますが、ここで有効なのが「論理的思考」です。
論理的思考は、「複雑なものをシンプルにしていく思考法」です。
正しい論理構造の組み立て方や、因果関係の捉え方も身に着けることができるので、相手が理解しやすいのみならず、納得性のある伝え方もできるようになります。
まとめ
「話がかみ合わないことが多いな...」と悩んでいる人は、どういうシーン・話題でかみ合わないのかを突き止めることから始めてみましょう。
原因を明らかにした上で、上記で紹介した対処法などを実践してみてくださいね。
著者情報

村尾 佳子(グロービス経営大学院 経営研究科 副研究科長)
関西学院大学社会学部卒業。大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策修士。高知工科大学大学院工学研究科博士(学術)。大手旅行会社にて勤務後、総合人材サービス会社にてプロジェクトマネジメント、企業合併時の業務統合全般を経験。現在はグロービス経営大学院にて、事業戦略、マーケティング戦略立案全般に携わる。教員としては、マーケティング・経営戦略基礎、リーダーシップ開発と倫理・価値観、経営道場などのクラスを担当する。共著に『キャリアをつくる技術と戦略』、27歳からのMBAシリーズ『ビジネス基礎力10』『ビジネス勉強力』『リーダー基礎力10』がある。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。