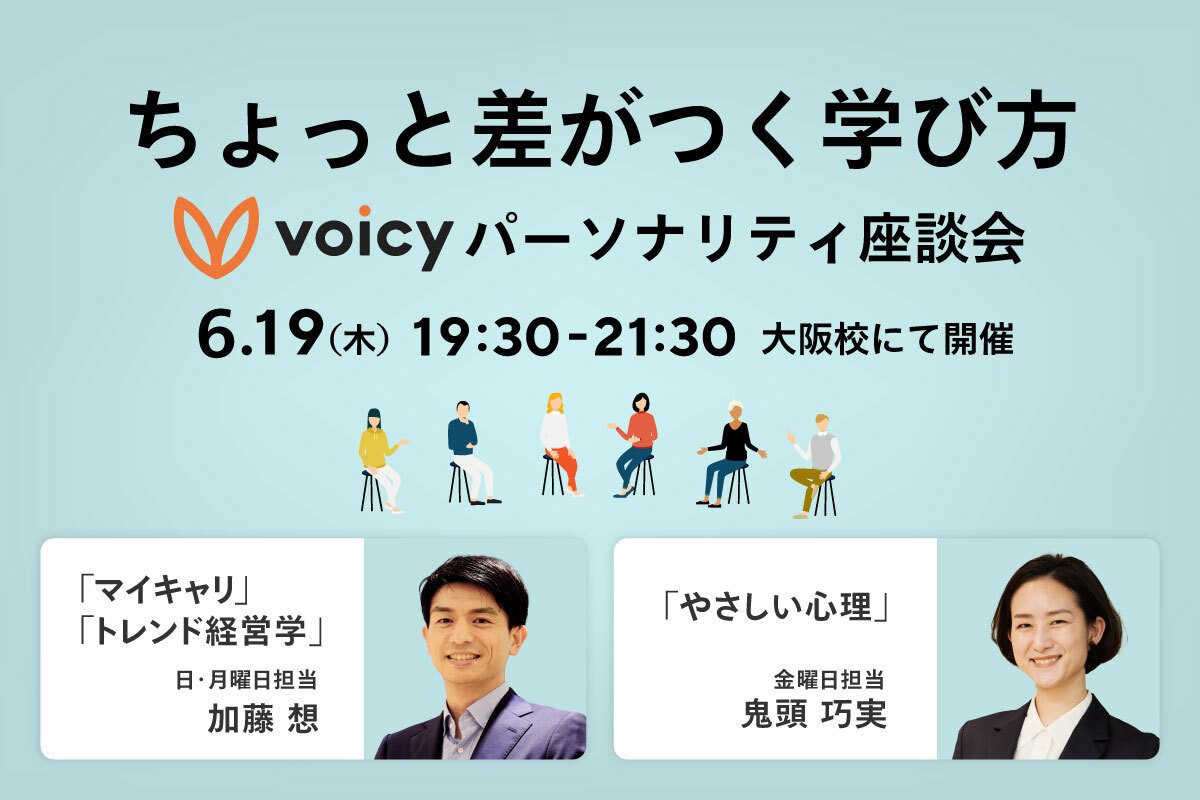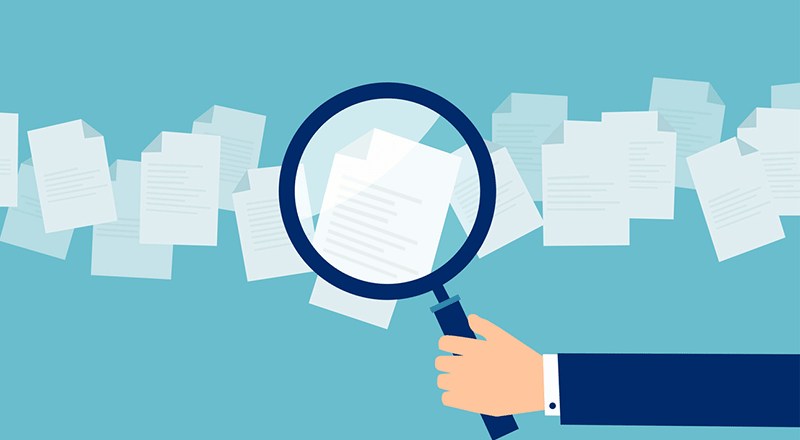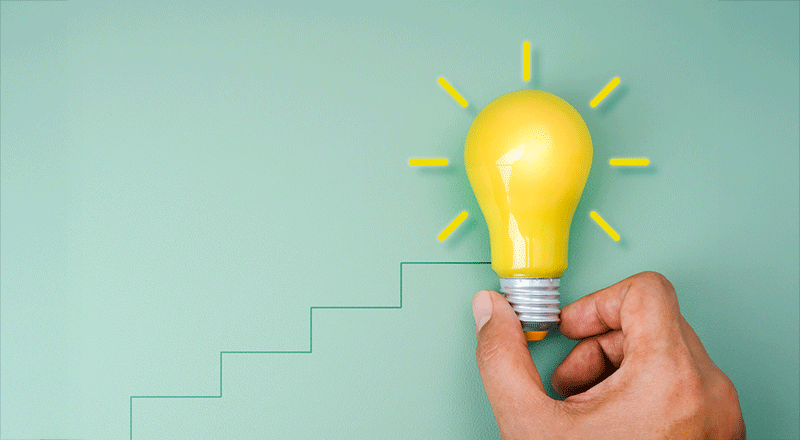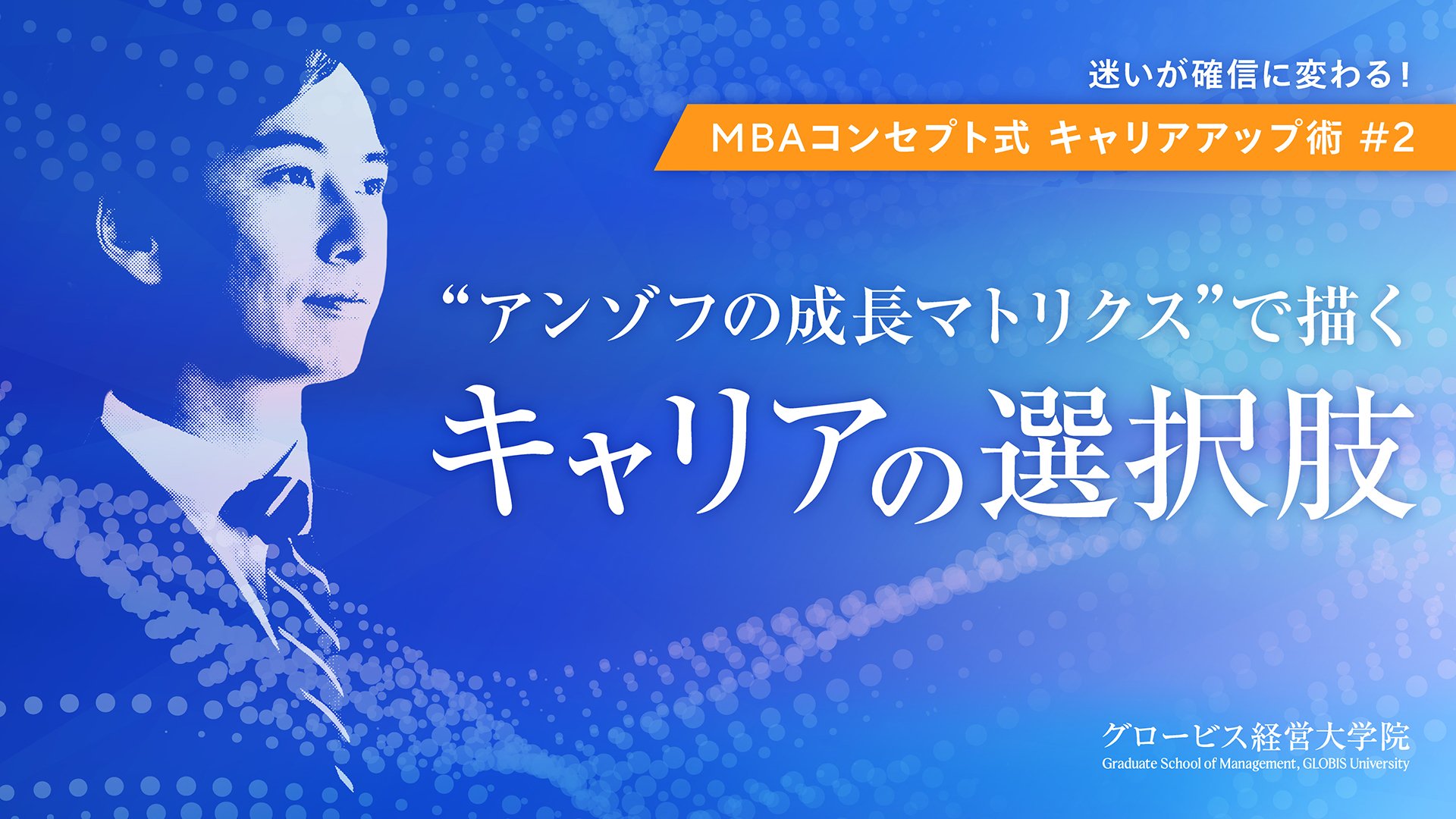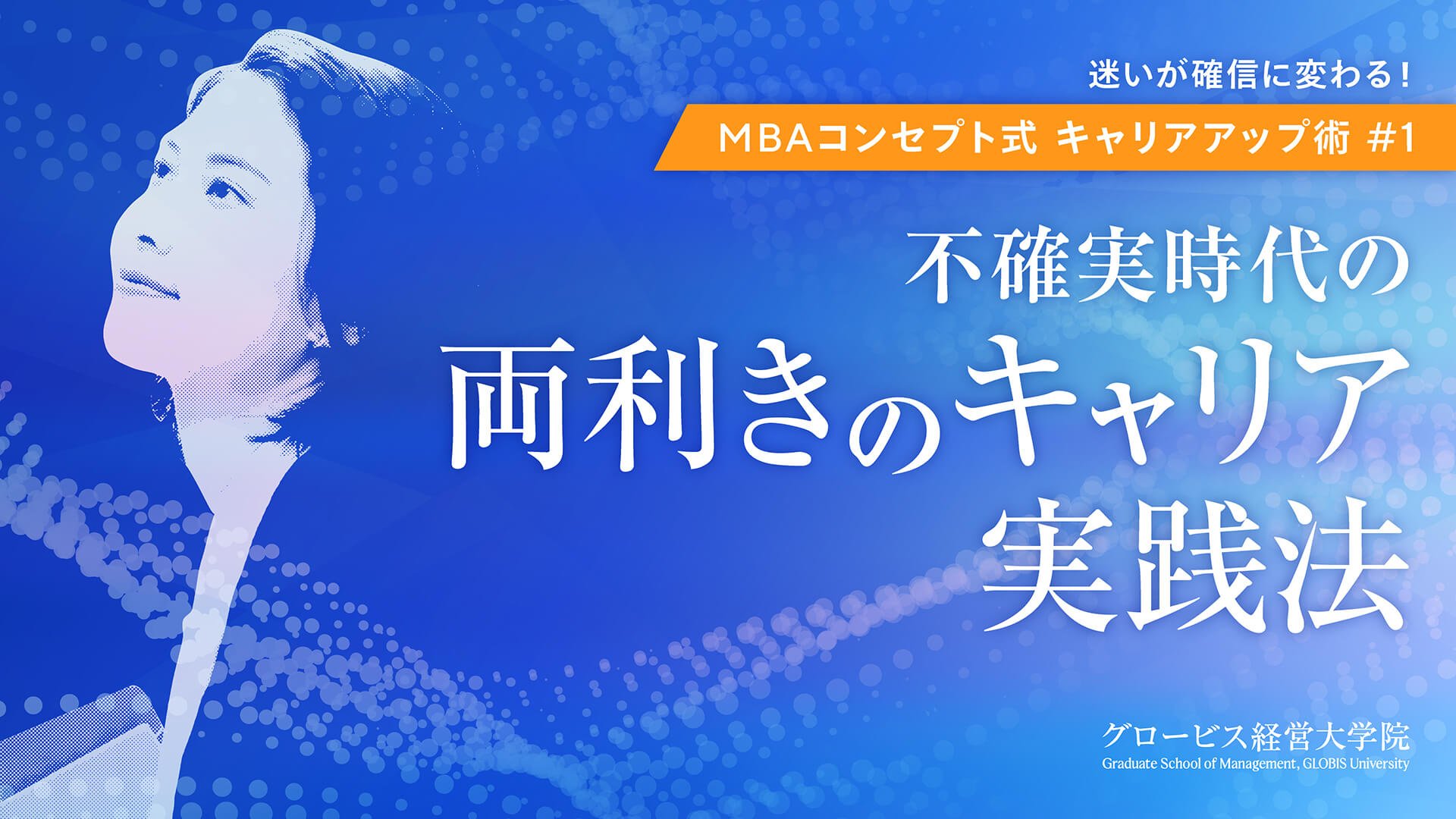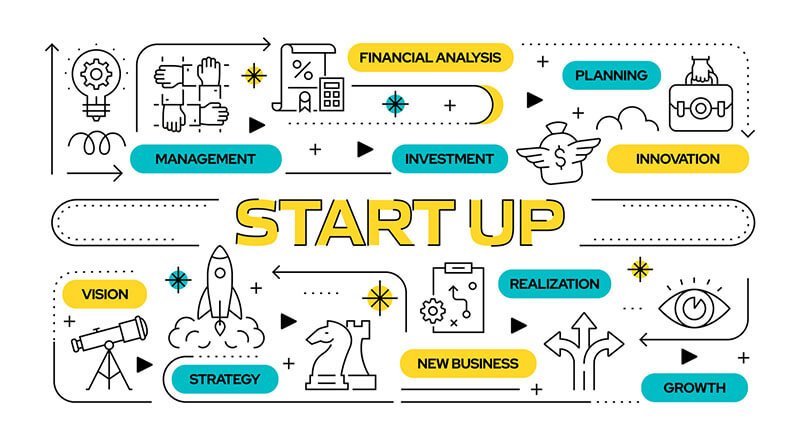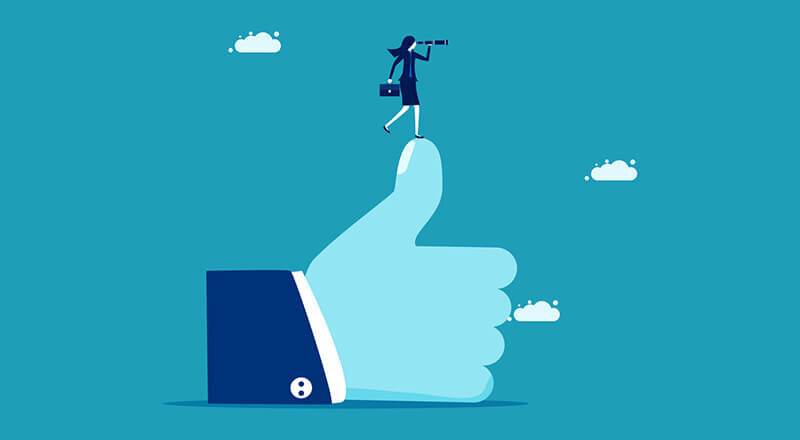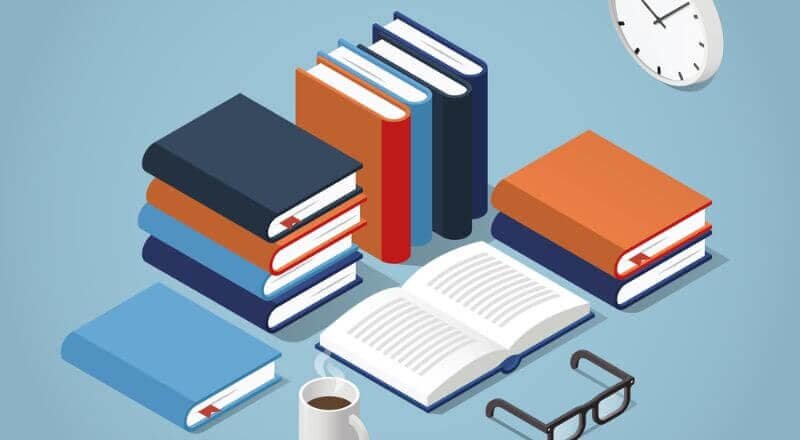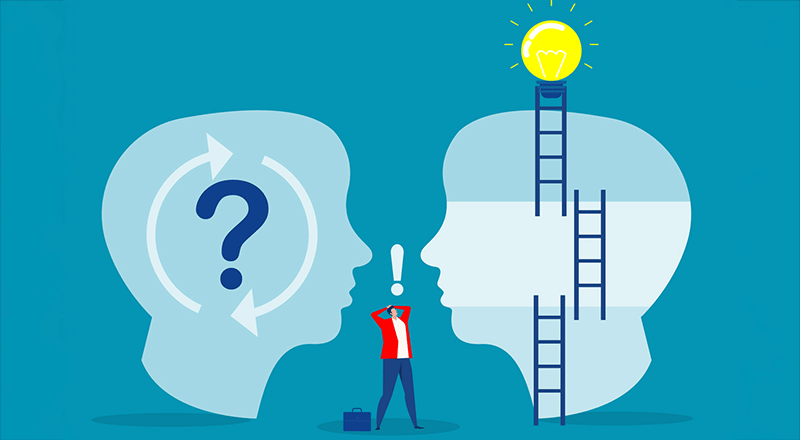
目次
「自分の専門ではない分野のチームをどうまとめればいい?」――そんな問いに、多くのマネジャーは心当たりがあるはずです。
プレイヤーとして実績を積み、リーダーに昇格すると、業務範囲は一気に広がります。すると、得意ではない分野や、全く経験のない業務にも関わる必要が出てきます。そんなとき、どうやってメンバーから信頼されるマネジメントをしていけばいいのでしょうか?
①手を動かして「現場感」を身につける
1つ目の方法は、「実務を自分でやってみる」ことです。短時間でもいいので、メンバーと一緒に手を動かすことが大切です。実務経験が少ないから苦手、というケースは意外と多いもの。やってみることで業務の大変さや課題が見え、メンバーの気持ちにも寄り添えるようになります。
そしてこの姿勢こそが、チームの信頼を育みます。「わからないからこそ、一緒にやってみる」。そんな謙虚なアプローチが、好循環を生むきっかけになるのです。
②"問いかけマネジメント"で自走力を高める
2つ目のアプローチは、「知らないことを前提にマネジメントを組み立てる」こと。リーダーはすべてを理解していなければならない――そんな思い込みを手放しましょう。
マネジメントの本質は、実務を完璧にこなすことではなく、チームの力を引き出すことです。たとえば、相談を受けたときに「どう思う?」と問いかけてみる。他のメンバーの意見を促す。あるいは、「なぜそう考えるのか?」と背景を深掘りしてみる。こうした対話が、メンバーの主体性を育て、チームの自走力につながっていきます。
「すべてを知っているマネジャー」である必要はない
マネジメントの立場になるほど、実務からは自然と離れていきます。だからこそ、「自分がすべてを把握していないといけない」というプレッシャーを感じる必要はありません。
大切なのは、「どうすればチームが自分で考えて動けるようになるか?」という問いを常に持ち続けること。リーダー自身が完璧でなくても、メンバーが成長できる環境をつくることこそが、優れたマネジメントなのです。
まとめ:できるかどうかより、「どう関わるか」が大事
マネジメントには、"すべての仕事を知っていること"よりも、"どんな状況でも関わり方を工夫できる柔軟性"が求められます。自ら手を動かしてみること、そして問いを通じてメンバーの思考を引き出すこと。この2つのアプローチを使えば、不慣れな領域でも十分にチームを導いていくことができます。
次に新しい領域を任されたときは、ぜひ「得意じゃないけど関われる」自分を信じて、一歩踏み出してみてください。
著者情報

熊谷 翔大
神戸大学発達科学部卒業。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。大手自動車メーカーにて、総務・人事部門にて、不動産管理や地域渉外、全社の労務管理に従事。また、全寮制の中高一貫校への出向も経験。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院・大阪校の責任者として、学生募集や学生の履修相談・キャリア支援、クラス運営のオペレーション等、大阪校全体のマネジメントを経験。現在は、グロービス・コーポレート・エデュケーションにて、組織開発・人材育成コンサルタントとして、組織・人づくり支援を行っている。
リーダーシップに関する教材開発や論理思考・リーダーシップ領域の講師も務める。グロービス経営大学院のVoicyチャンネル「ちょっと差がつくビジネスサプリ」では、水曜日パーソナリティを担当。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。