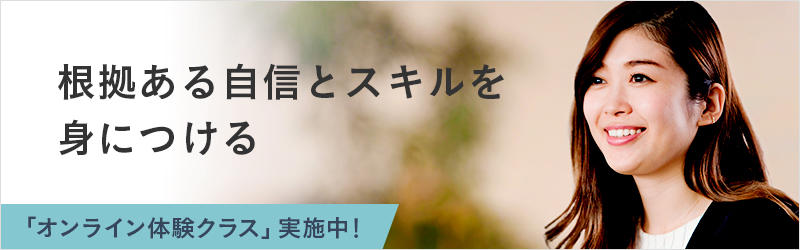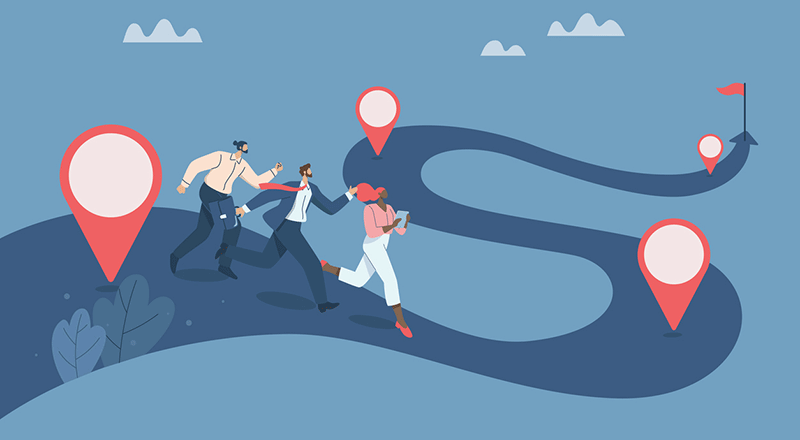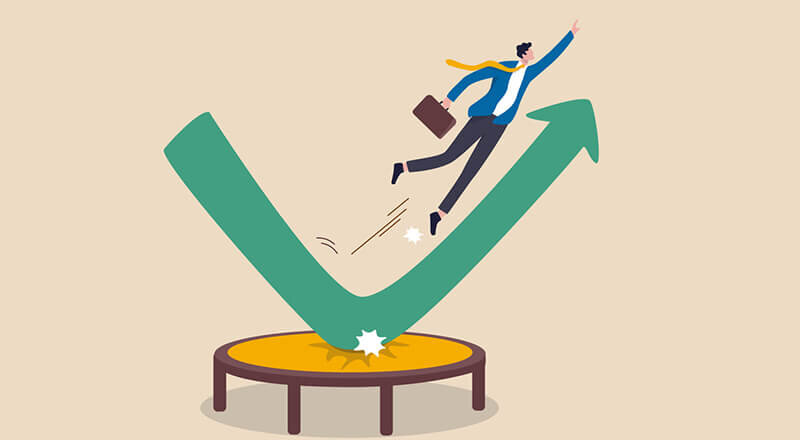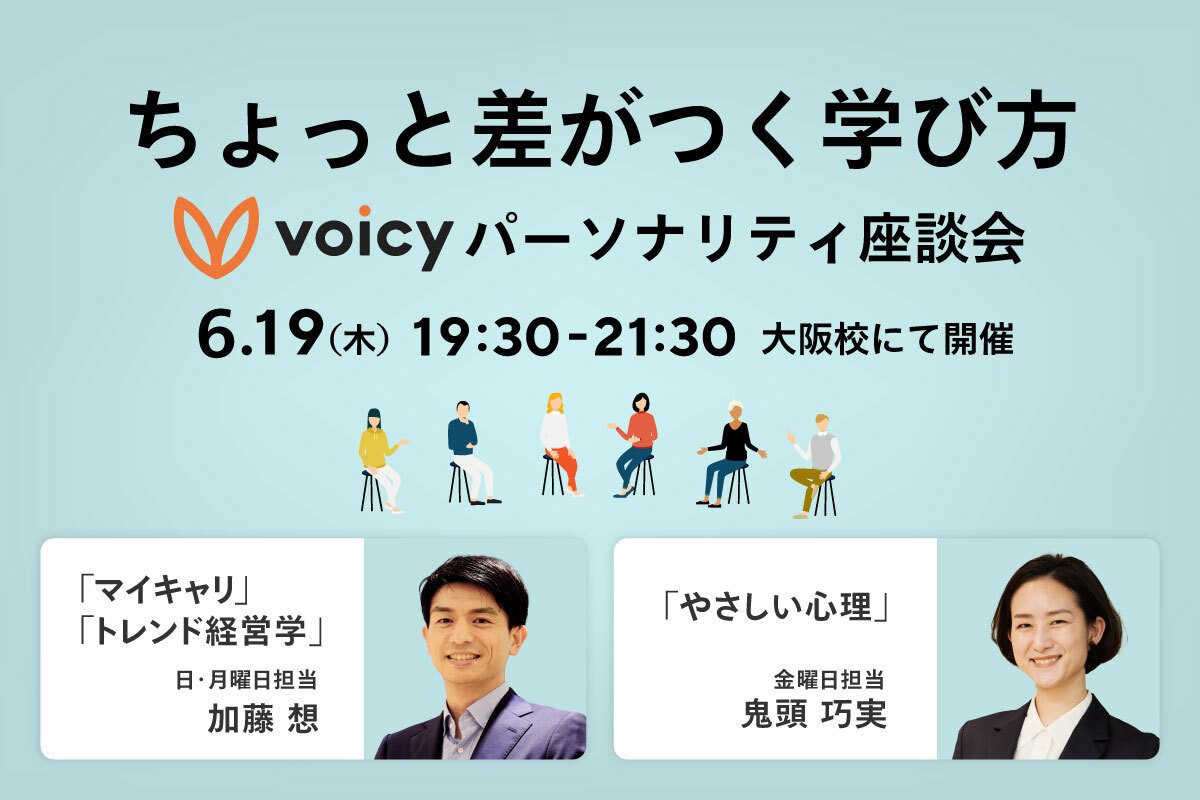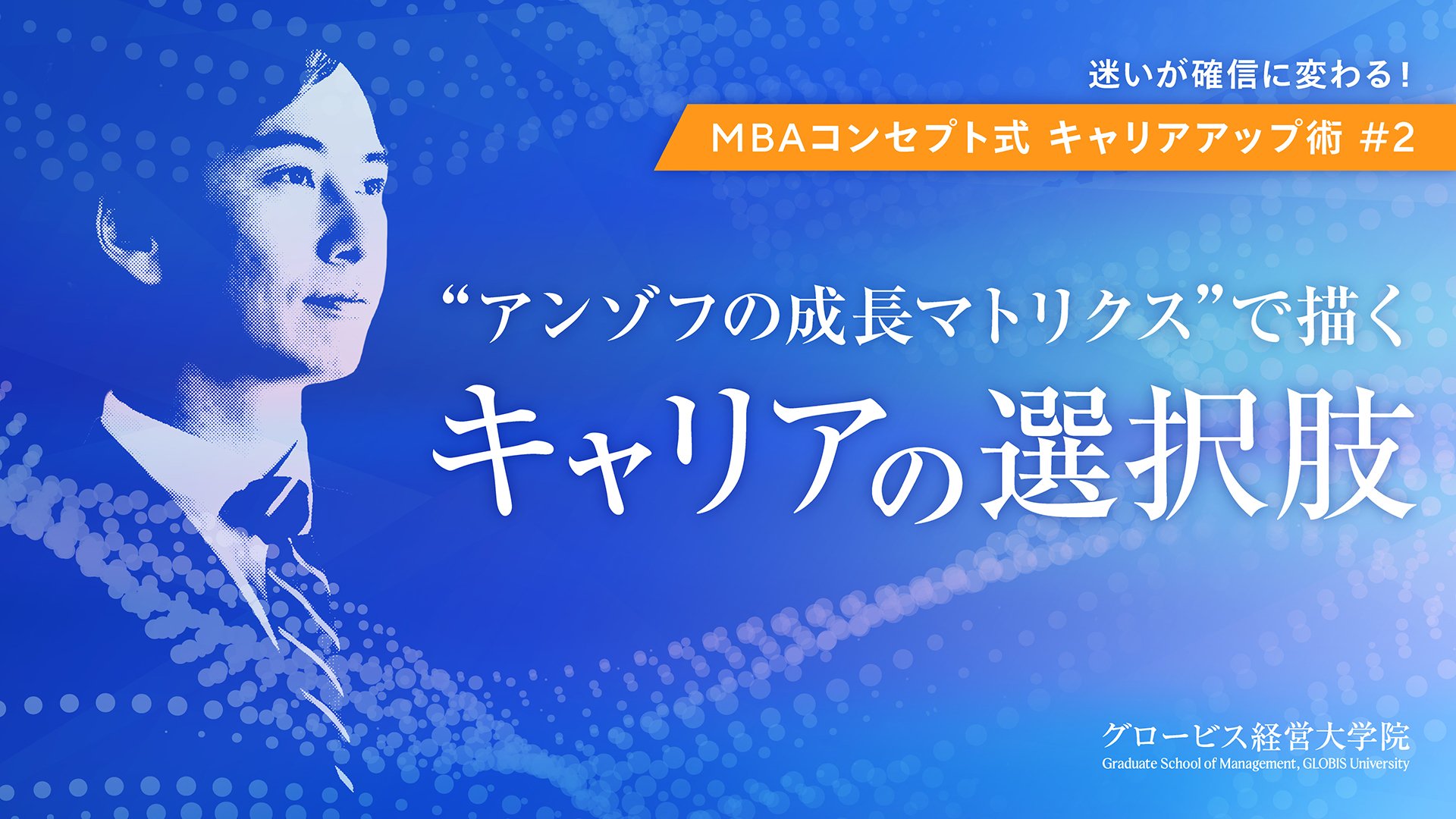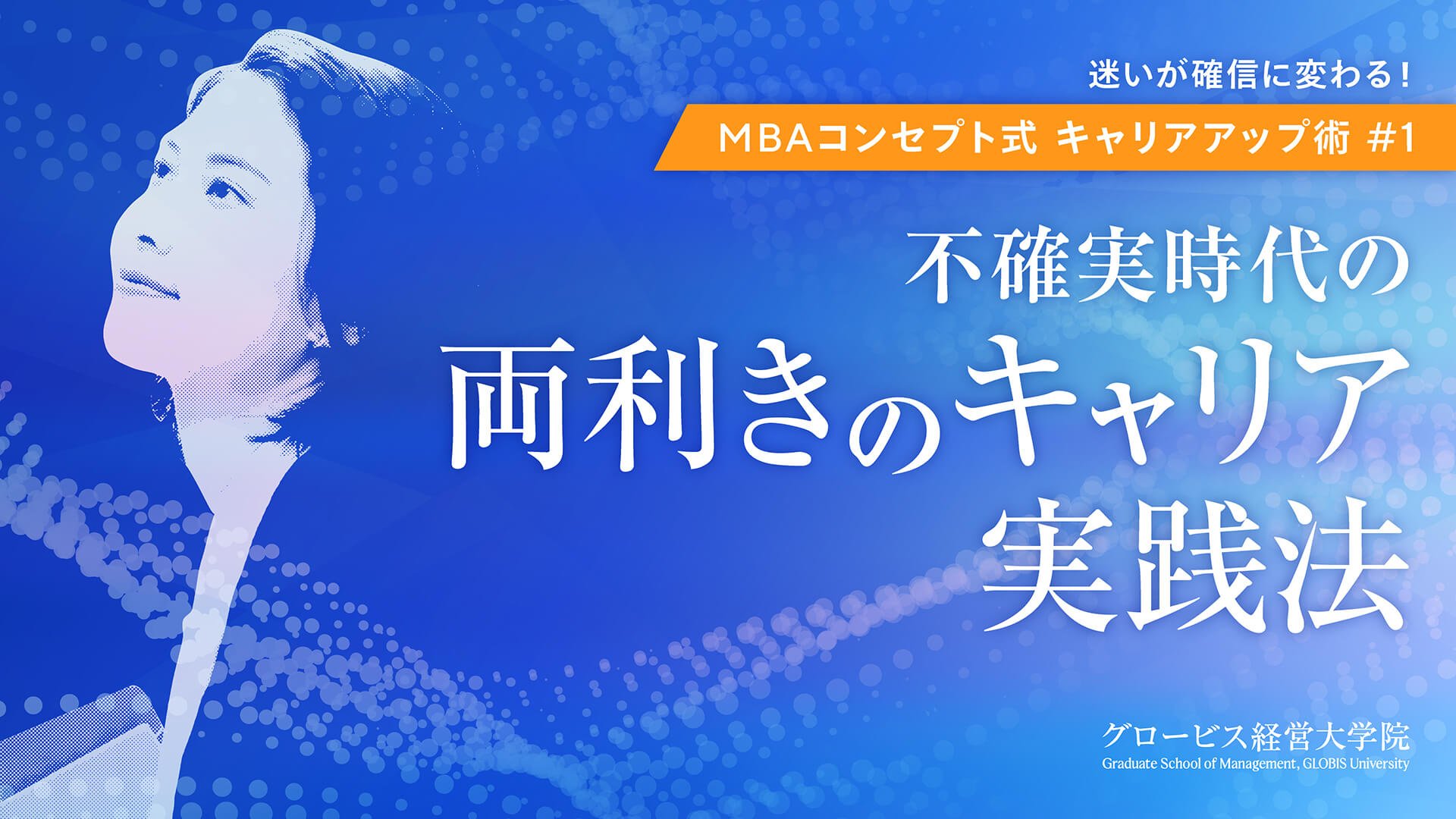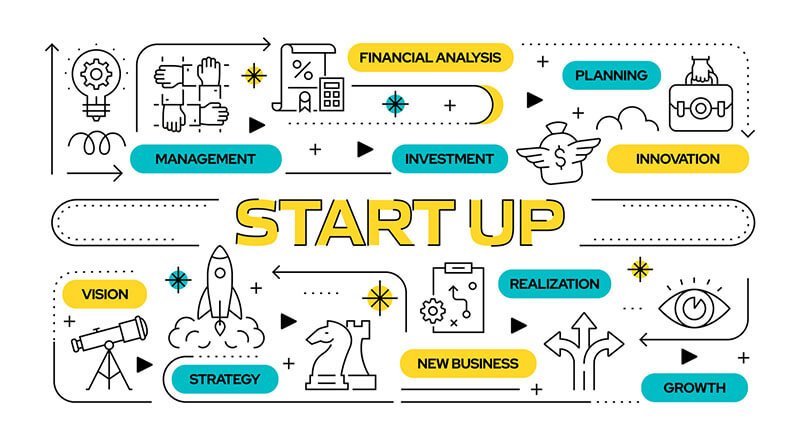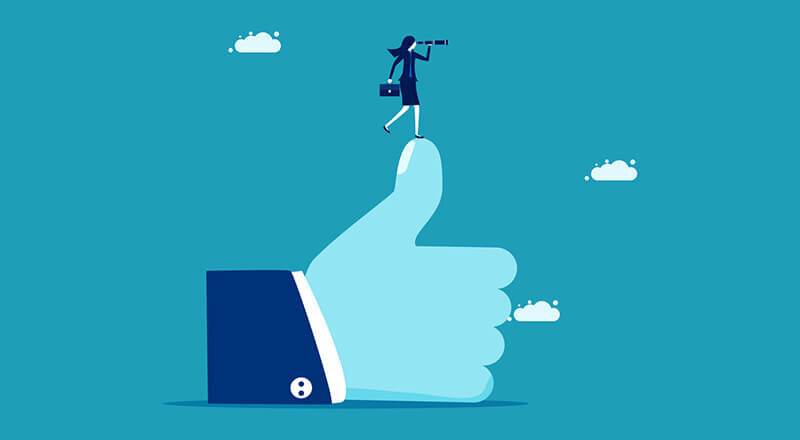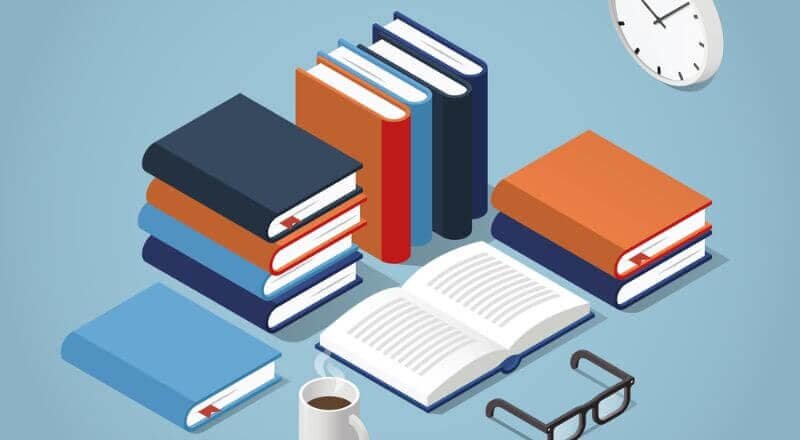目次
「あ~今日は仕事行きたくないなぁ」
「今の会社辞めたいなぁ」
心の中でそう呟きながら出勤したことって、ありませんか?
楽しいことばかりではないのが、仕事。
でも、毎日のように感じるようになったら、根本的な現状の見直しや、場合によっては心身のケアが必要になります。
「仕事がつらい」と感じた時の対処法を考えてみましょう。
「仕事がつらい」と感じるのは甘えなのか?
自分を責め過ぎない
「仕事がつらいと感じるのは、自分の意志力が低いせいではないか?」
「ここで逃げ出してしまったら、どこに行っても通用しないのではないか?」
そう自分を責めてしまったことはありませんか。
上司や親から「石の上にも三年だ」と諭され、つらくてもひたすら現状に耐える。
周囲の先輩や同僚はみな優秀で、自分だけ弱音を吐くことはできない。
社会人歴の浅い若手社員を中心によくみられる光景です。
たしかに逃げ癖がつくのはよくないことですし、そう思い悩むのは心根が真面目な証でもありますが、長期間過剰なストレスがかかり続けると心身の健康にも影響があります。
「仕事がつらいと感じるのは甘えかも」と自分を責めすぎずに、心身のSOSにも耳を傾けるようにしましょう。
謙虚さも忘れないように
とはいえ、「甘え」かどうかは、往々にして周囲の評価で決まってしまいます。
特に上司や先輩は、かつて同じ道を通っただけに、「当時の自分」という評価軸を持っています。
遅刻や同じミスを繰り返すなど、社会人としての常識が欠けていると判断された場合は、「甘えている」と受け取められかねません。
人との接し方の習慣や考え方は、世代によって差があります。
自分に非がなくても、周囲からネガティブに受け止められ、仕事がやりづらくなるということもあります。
多かれ少なかれ、誰もが常識外れの面を持ち合わせていると思いますが、必要以上にマイナス評価を受けないためにも、耳が痛いことも受け入れる謙虚さを忘れないことも重要です。
仕事がつらい人のSOSサイン
仕事がつらいと感じている状態は、心や体、そして行動にもさまざまなサインとして現れます。見逃してしまうと、心身に大きな影響を及ぼすこともあるため、早めに気づくことが大切です。ここでは、「心」「体」「行動」に分けて、主なSOSサインを紹介します。
心のSOS
以下のような感情や思考パターンが頻繁に現れる場合、心が限界に近づいているサインかもしれません。
- 朝起きると強い憂うつ感がある
- 何をしても楽しいと感じられない
- 理由もなくイライラする、怒りっぽくなる
- 自分を必要以上に責めてしまう
- 以前よりも涙もろくなった
体のSOS
メンタルの不調は、身体にも直接的な影響を与えます。以下のような変化があれば、心と体の休息が必要な状態です。
- 慢性的な頭痛や肩こりが続いている
- 胃の不調や食欲の低下/過剰
- 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める
- 倦怠感が続き、起き上がるのがつらい
- 動悸や息苦しさを感じる
- 突然のめまいや立ちくらみ
行動のSOS
行動の変化は、周囲も気づきやすい重要なサインです。以下のような傾向がある場合は、早めの対処をおすすめします。
- 遅刻・欠勤が増える
- 仕事への意欲が著しく低下する
- これまでできていたことがうまくできなくなる
- 人と関わるのを避けるようになる
- 趣味や好きだったことにも関心が持てない
- 食べ過ぎや飲酒量の増加など、自暴自棄な行動が目立つ
仕事がつらいと感じる時の代表的な原因
84%が「働きたくない瞬間がある」
「仕事が嫌だ」と思うことは、おかしなことでしょうか?
株式会社ビズヒッツが実施したアンケート調査(対象:10代~50代の働く男女1000人)によると、実に84%が「働きたくないと思う瞬間がある」と回答しています。
かくいう私も「働きたくない」と感じた瞬間があります。
個人的には、NOと答えた人が16%もいることに少し驚きました。
一番の理由は、人間関係
では、その理由は何でしょう?
- 1位:人間関係がつらい(23.1%)
- 2位:疲れる、体がつらい(14.7%)
- 3位:休みがない、残業が多い(11.8%)
- 4位:やりがいがない(6.8%)
- 5位:上司が嫌い(6.5%)
という結果になっています。
6位以下には「給料が安い」「家事との両立が大変」といった生活にも影響してくる理由が挙げられていました。
「人間関係がつらい(1位)」と「上司が嫌い(5位)」、「疲れる(2位)」と「休みがない(3位)」は、それぞれ共通点がありますね。
まとめると、「働きたくない」と思う主な理由は、大きく2つの方向性「職場の人間関係」「心身への負担」と言えそうです。
働きたくないと思う理由は人それぞれですし、深刻さもまちまちです。
しかし、社会人をしていると、人間関係の摩擦や業務負担へのストレスは避けられない問題です。
そういった意味では、「働きたくない」という気持ちが湧くのは自然なことだと思います。
解決法は、異動?それとも転職?
ただ、回答の中には「働かずに暮らしたい(4.2%)」「朝起きるのが辛い(4.1%)」といった理由を挙げた人も一定数いました。
気持ちは理解できますが、給料をもらう以上、最低限の心構えは必要かと思います。
特段の理由がないのに朝起きられない人を、いつまでも雇い続ける会社は限られるでしょう。
職場で人事異動や配置替えがあれば、人間関係や業務負担などの問題は、解決できる可能性があります。
もしも興味がある仕事や部署があれば、積極的に希望を出すというのも1つの手です。
一方、「やりがいがない」「給料が安い」といった問題が、自分の所属部署だけじゃなく、会社全体、もしくは業種全体で共通するような状況であれば、解決は困難です。
場合によっては、転職も視野に入れた方がよいかも知れません。
仕事がつらいと感じたときの対処法
信頼できる人への相談
悩みを聞いてくれる人の存在は、仕事に限らず貴重です。
愚痴を言ってスッキリしたい時もあれば、具体的なアドバイスが欲しい時もあるでしょう。
本音を明かすことで、気持ちが整理ができたり、自分の立ち位置を確認したりできることもあります。
原因が自分にあるのか、周囲の環境にあるのかなど、客観的な意見を聞くことでみえてくることもあります。
具体的なアドバイスがほしい方は、「メンター」をつくることをおすすめします。
メンターとは、日本語で「指導者」。
自身が仕事やキャリアの手本となって、新入社員や若手社員に助言・指導をし、個人の成長や精神的なサポートする人のことです。
近年、離職率の防止や人材育成の観点で注目され、メンター制度として導入する会社も増えています。
メンターは、同じチームや他部署の先輩社員が担当するケースが多いです。
制度として導入されいない場合は、自ら「メンターをしてくれませんか?」と頼むのもいいでしょう。
もちろん、社外で探すのもおすすめです。
こちらの記事で、メンターのメリットや役割について詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
人事異動
仕事がつらく感じる理由が人間関係にある場合、苦手な人と距離を置くことが解決策の一つになりえます。
会社のルールの則り、上司や人事担当者に異動や配置換えを相談するのも一つの手です。
ただし、異動が伴うことで、人間関係のヒビが決定的になることもあります。
冷静に考えた上で慎重に行動に移した方がよいでしょう。
また、明らかにパワハラなどのハラスメントを受けていたり、業務の妨げになるような嫌がらせを受けている場合は、人事に相談をしてもよいかもしれません。
休職、転職
「今の会社にいるのがつらくてどうしようもない」
そのような場合は、休職や転職を検討してみましょう。
休職は、自分と向き合い、心身を休める時間を作るのに良い方法です。
転職は、生活全般に影響が及ぶので、覚悟や家族の理解が必要ですが、自分の可能性を信じて飛び出すのであれば、むしろ前向きな良い決断だと思います。
最近は、日本の雇用慣習である終身雇用が、崩れつつあります。
社会の変化が激しい中、同じ会社に勤め続けることは、将来的なリスクになる可能性もあります。
ただし、嫌だからその場から離れるのではなく、現職で学べることはしっかりと吸収しながら、自分の今後のキャリア形成をイメージしつつ、判断を下すのが理想だと思います。
自分らしい働き方を探すヒント
「仕事がつらい」と感じたときこそ、自分自身と向き合う貴重なタイミングでもあります。つらさの原因を整理し、これからどうしたいのかを考えることで、自分をより良い方向に変えていくきっかけになります。
そんなときこそ、社外の人と話すことが、気づきや整理の助けになる場合があります。職場の事情を知らない第三者だからこそ、フラットな視点で話を聞いてもらえたり、自分では考えつかなかった選択肢が見えてきたりすることもあるでしょう。
たとえば、勉強会やキャリアに関するイベントなどに参加してみるのも一つの方法です。グロービス経営大学院が開催している「体験クラス&説明会」も、キャリアを見直す場として活用されています。さまざまな業種・職種の人と対話する中で、自分自身の価値観や働き方について見つめ直すきっかけになるかもしれません。
▼体験クラス&説明会(無料)のお申し込みはこちら
まとめ
かのイチロー選手も、アメリカで活躍していたころ、帰国して日本でプレーすることを真剣に考えた時期があったそうです。
原因は、やはり人間関係。
チームが低迷していた時期に、個人では堅調な成績を維持していたためか、チームメイトとの関係が悪化。
「同じユニフォームを着ていても、全員敵」とまで感じたそうです。
スーパースターですら内部の人間関係に悩むのですから、ビジネスパーソンが悩むのは当然ですね。
仕事をつらく感じる時は、良くも悪くも、自分が変わるきっかけです。
ぜひとも、悲観しすぎることなく、目の前の壁に謙虚に向き合うことで、自分をいい方向に成長させてください。
著者情報

川崎 弘
横浜国立大学経済学部卒。西日本新聞社(福岡市)入社。事件、経済、街ダネを中心に13年の記者生活を経て、妻の実家の醤油屋「合名会社まるはら」(大分県日田市)入社。2020年、グロービス経営大学院修士課程修了(MBA)。「批判より行動を」「報道より行動を」を合言葉に、人口が減る中で地方の雇用の場をどうやって守るかを日々考えています。佐賀市出身。カレーとラグビーが好き。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。