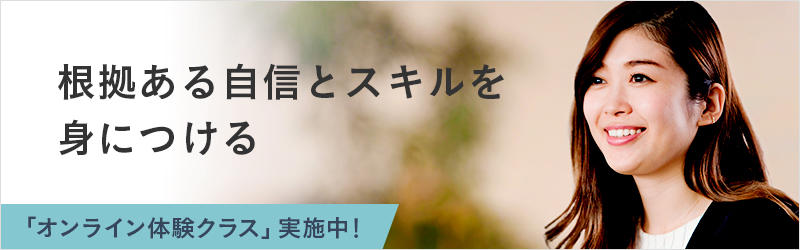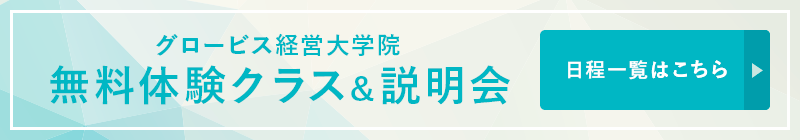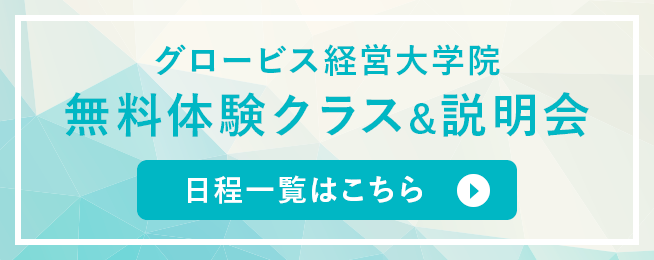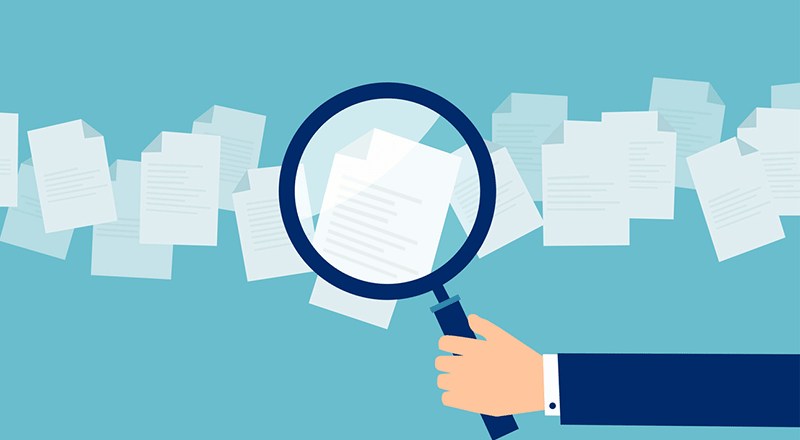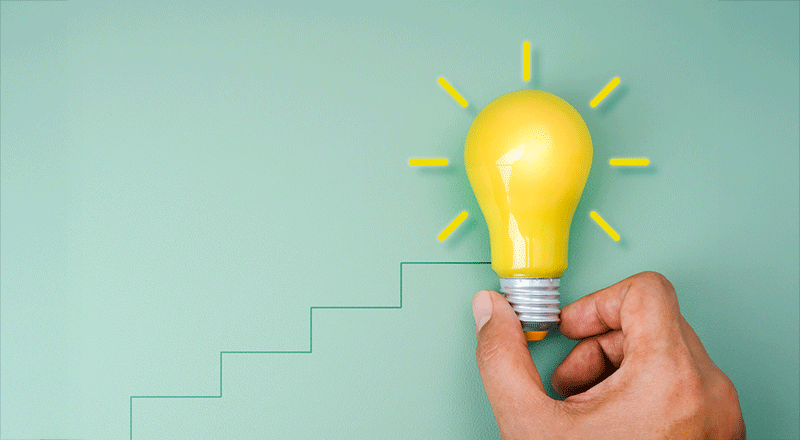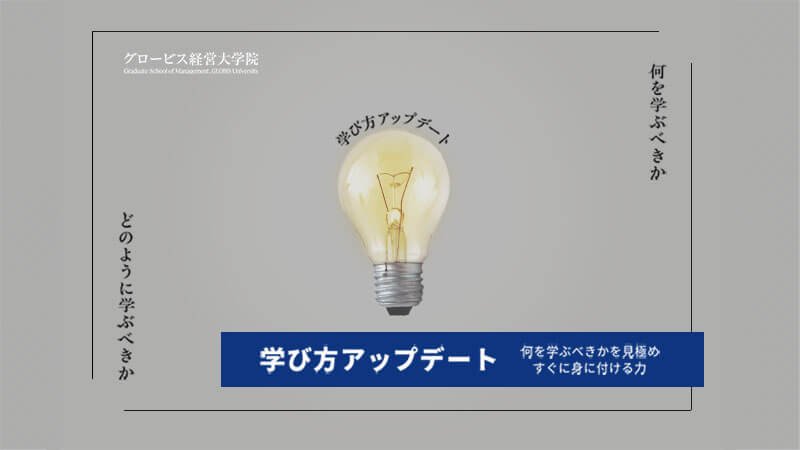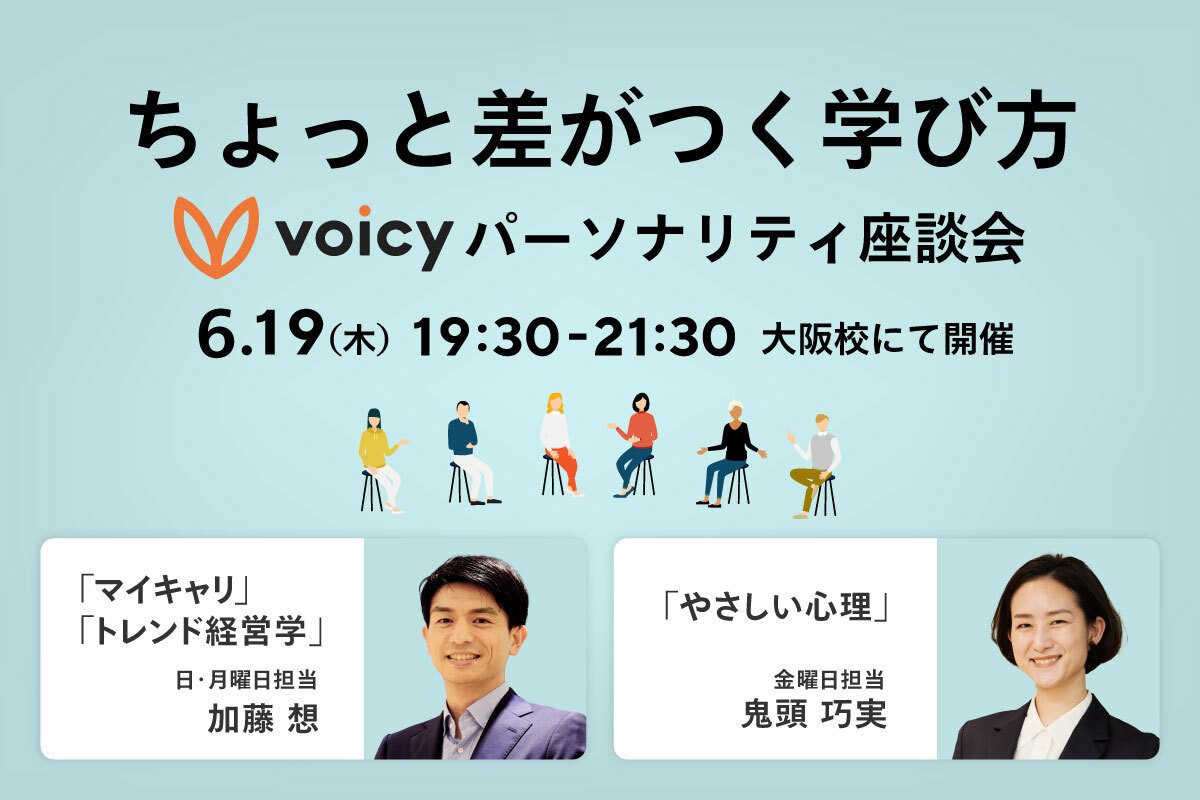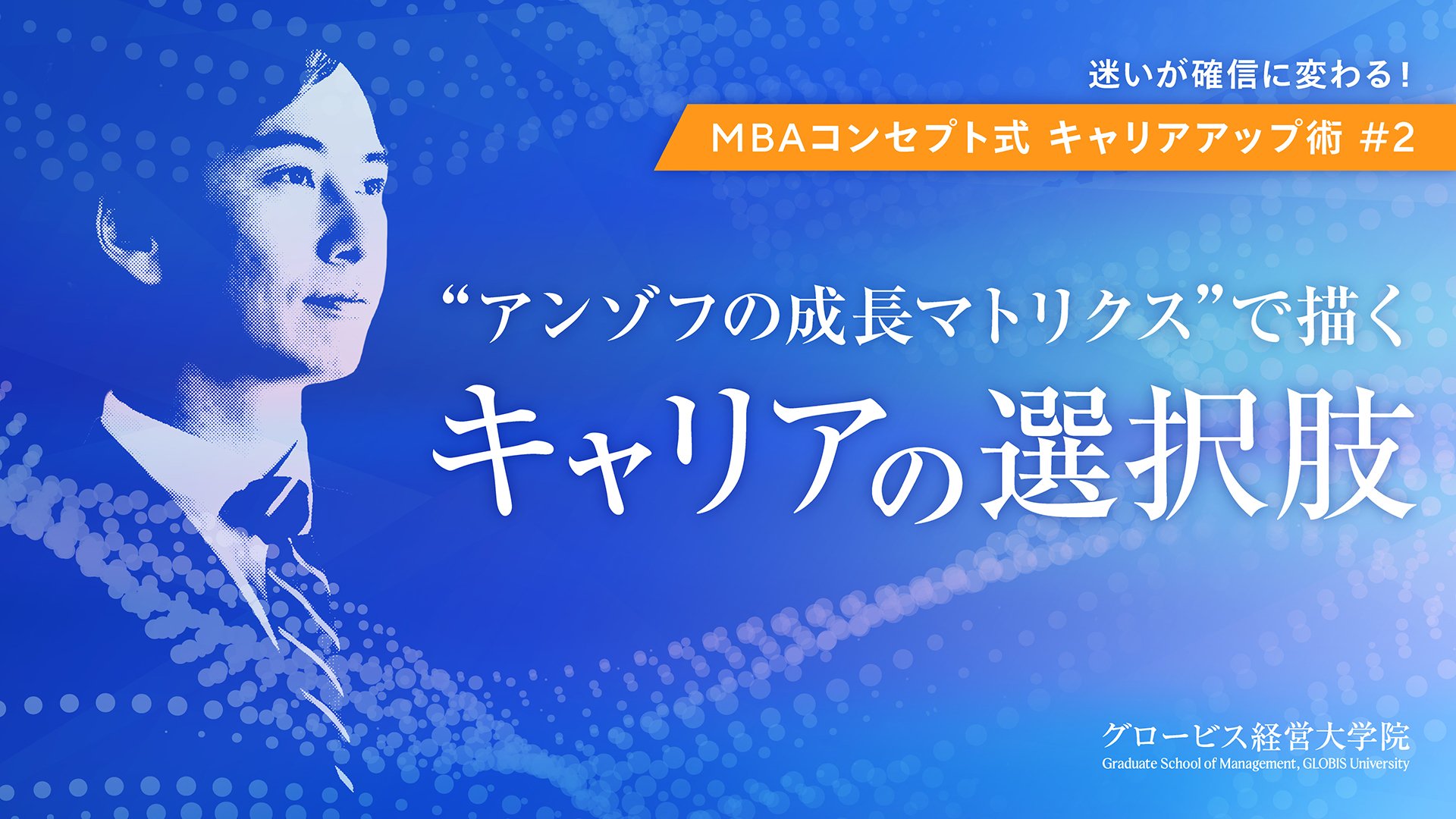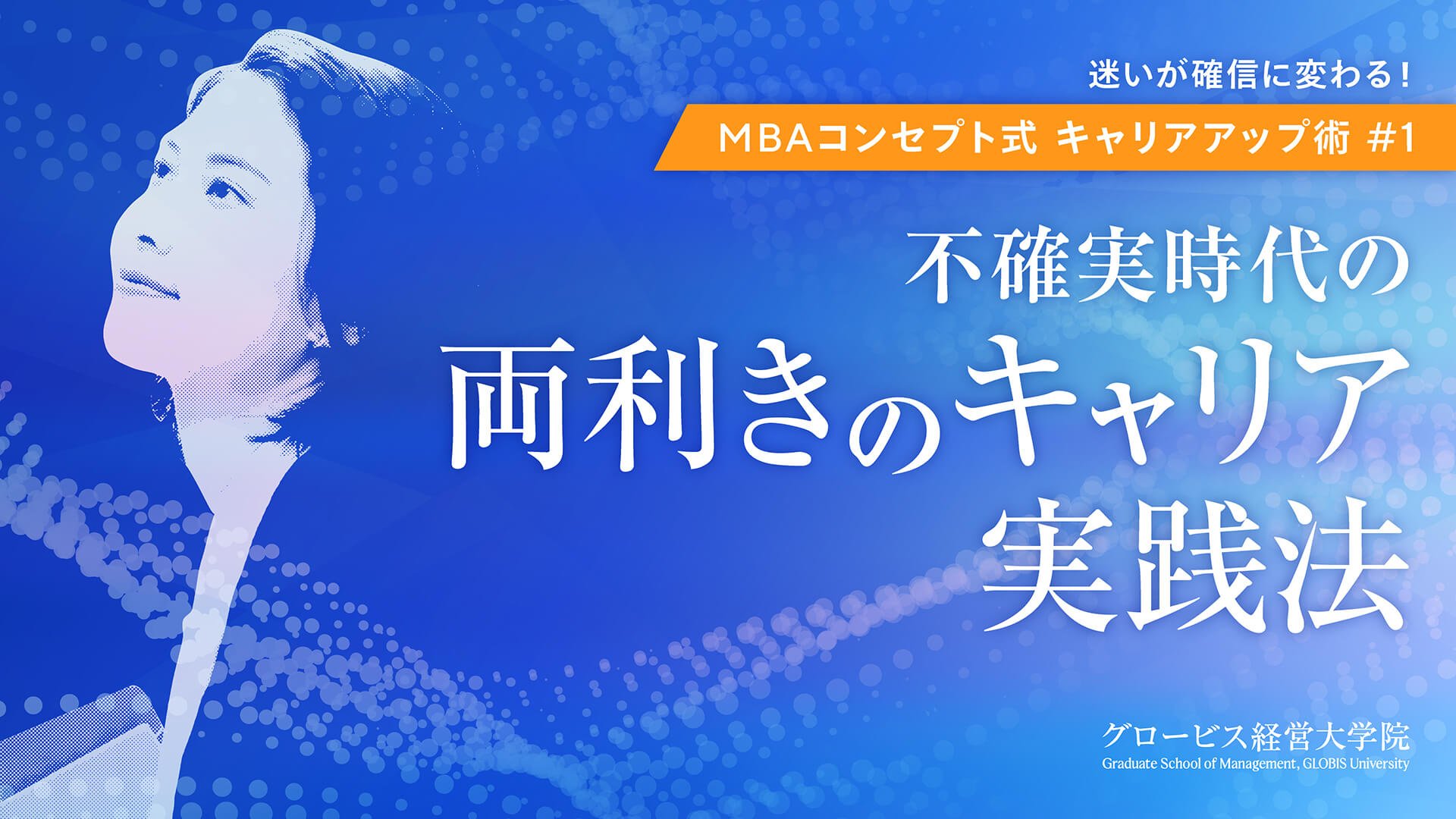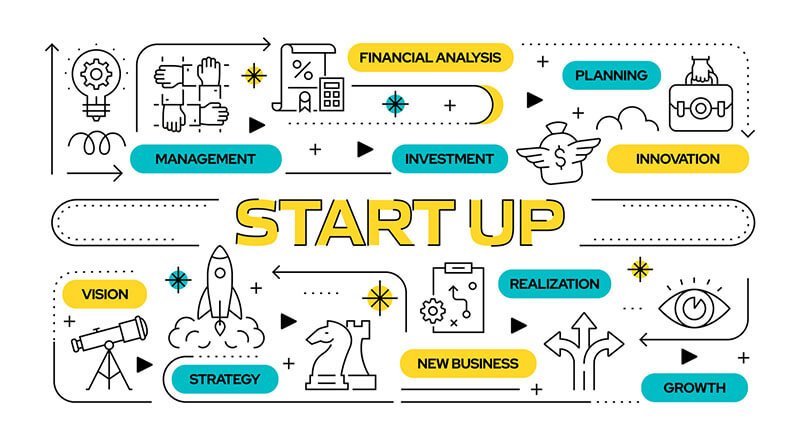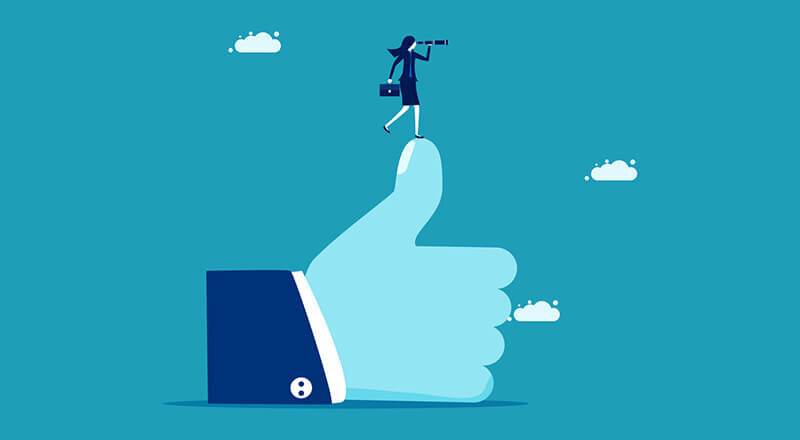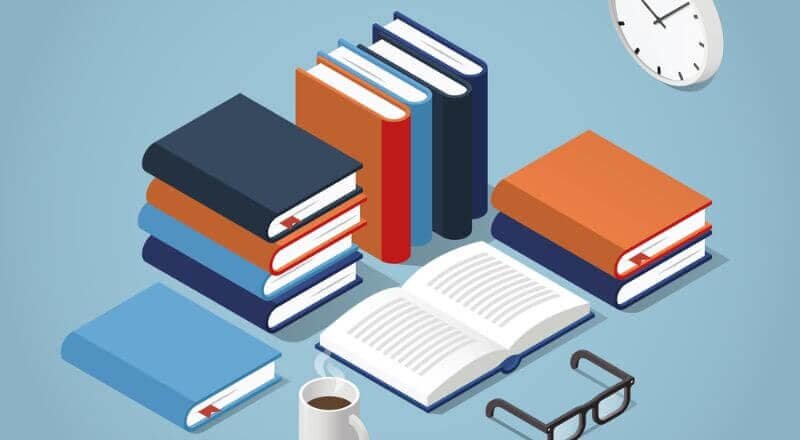目次
4月から始まった新年度。
新たに社会人になる人もいれば、先輩として後輩の育成を任される人もいて、期待と不安とが入り混ざる時期かもしれません。
「はたして自分は会社に求められる人材になれるだろうか?」
「4月から新人教育を任されたが、自分自身のスキルは足りているだろうか」
様々な想いを胸に始まる新年度は、自分を見つめなおすには良いタイミングです。
そこで今回は、自分自身のスキルを確かめる上で参考になる「社会人基礎力」についてご紹介します。
社会人基礎力とは?簡単に解説
「社会人基礎力」とは、経済産業省が提唱する「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」です。
これは、「前に踏み出す力」(主体性、働きかけ力、実行力)、「考え抜く力」(課題発見力、計画力、創造力)、「チームで働く力」(発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力)という3つの能力と、それらを構成する全12の能力要素から成り立っています。
これからの人生100年時代を生き抜く上で、自らキャリアを築き、社会で活躍し続けるための土台となる重要なスキルです。幅広い年齢層のビジネスパーソンに必要なスキルとなっています。
社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素
では、社会人基礎力とは、具体的にどのような力のことを指すのでしょうか。
社会人基礎力を構成する3つの能力と12の能力要素についてご紹介します。
能力①:前に踏み出す力(アクション)
「一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力」と定義されている能力です。
例えば、学校の勉強では正解が1つと決まっているものが多くありますが、実社会で仕事をしていると、正解が1つに決まっているケースは極めて少ないものです。
そのため、正解が分からない中でも失敗を恐れずに前に踏み出す力が求められます。
仮に失敗しても、周りの人の協力を得ながら試行錯誤を繰り返し、粘り強く取り組むことが大切です。
そのために必要な能力要素が3つあります。
- 主体性:物事に進んで取り組む力
- 働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力
- 実行力:目的を設定し確実に行動する力
主体性とは何か
主体性とは、与えられた指示を待つのではなく、自ら考え、判断し、積極的に行動を起こしていく力です。
目標達成や課題解決に向け、周囲の状況を的確に把握し、自らの意思で責任を持って行動を選択する姿勢を指します。
「言われたことをこなす」だけではなく、「何をすべきか」「どうすればより良くなるか」を自律的に考え、行動に移すことで、自身の成長はもちろん、組織やチームに新たな価値をもたらすことができます。
変化の激しい現代において、あらゆるビジネスシーンで求められる重要な能力です。
働きかけ力とは何か
働きかけ力とは、目的達成のために、周囲の人々や関係部署を巻き込み、協力を促す力です。
単に依頼するだけでなく、相手の立場や状況を理解した上で、建設的なコミュニケーションを通じて、共に課題解決や目標達成へと導くことを指します。
この力は、多様な専門性を持つメンバーと連携したり、部署間の壁を越えてプロジェクトを進めたりする際に不可欠です。
周囲を動かすことで、一人では成し得ない大きな成果を生み出し、組織全体のパフォーマンス向上にも貢献します。
実行力とは何か
実行力とは、設定した目標や計画に対し、確実かつ迅速に行動し、成果を出す力です。
単に「行動する」だけでなく、困難な状況に直面しても粘り強く取り組み、途中で諦めずに最後までやり遂げる姿勢を含みます。
この能力は、計画を絵に描いた餅で終わらせず、具体的な結果へと結びつけるために不可欠です。
目標達成に向けた障害を乗り越え、試行錯誤しながらも前進し続けることで、個人や組織の成長を加速させます。どんなに優れたアイデアも、実行力がなければ価値を生み出すことはできません。
能力②:考え抜く力(シンキング)
これは「疑問を持ち、考え抜く力」と定義されています。
課題を解決したり物事を改善したりするためには、常に問題意識を持ち課題を発見しなければなりません。
そして、課題をどうすれば解決できるのかという疑問を持ち、自律的に深く考える必要があります。
そのために必要な能力要素が3つあります。
- 課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力
- 創造力:新しい価値を生み出す力
- 計画力:問題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
課題発見力とは何か
課題発見力とは、現状を多角的に分析し、表面的な問題の奥に潜む本質的な課題や、改善の機会を見つけ出す力です。
単に与えられた問題を解決するだけでなく、「なぜこうなっているのか」「もっと良い方法はないか」と疑問を持ち、自ら問いを立てることで、潜在的なニーズや未解決の課題を明確にします。
この能力は、ビジネスにおける新たな価値創造や効率化の第一歩となります。
複雑な状況の中から核心を見抜き、具体的な課題として設定することで、効果的な解決策の立案へと繋げることができます。
創造力とは何か
創造力とは、既成概念にとらわれず、新しいアイデアや解決策を生み出す力です。
既存の知識や情報を組み合わせたり、異なる視点から物事を捉えたりすることで、革新的な発想を導き出します。
この能力は、単なるひらめきだけでなく、論理的思考や柔軟な発想力を通じて、具体的な形に落とし込むプロセスを含みます。
変化の速い現代において、前例のない課題に直面した際や、競合との差別化を図る上で不可欠な要素であり、新たな価値やサービスを生み出す原動力となります。
計画力とは何か
計画力とは、目標達成に向けて、具体的な手順や必要な資源、スケジュールなどを論理的に組み立てる力です。
漠然とした目標を、実行可能なタスクに細分化し、優先順位をつけ、予期せぬ事態にも対応できるような柔軟性を持たせた計画を策定します。
この能力は、目標への最短ルートを見つけ出し、無駄なく効率的にプロジェクトを推進するために不可欠です。
リスクを事前に予測し、代替案を準備することで、計画の実行中に発生する問題にも冷静に対処し、着実に成果へと繋げることができます。
能力③:チームで働く力(チームワーク)
これは「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」と定義されています。
個人で大きな成果をあげようとしても、一人でできることには限界があります。
そこで、多様な人との協働が求められます。
多様な人と協働するためには、自分の意見をわかりやすく相手に伝えることはもちろん、相手の意見や立場を尊重し目標に向けて協力しあうことが必要です。
そのために磨いておきたい能力要素が6つあります。
- 発信力:自分の意見を分かりやすく伝える力
- 傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力
- 柔軟性:意見の違いや立場の違いを理解する力
- 情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
- 規律性: 社会のルールや人との約束を守る力
- ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力
発信力とは
発信力とは、自分の意見や考え、情報を相手に分かりやすく明確に伝える力です。
単に話すだけでなく、相手の理解度や関心に合わせて言葉を選び、論理的に構成することで、意図が正確に伝わるように工夫する能力を指します。
この力は、会議でのプレゼンテーション、チーム内での報告、顧客への説明など、あらゆるビジネスシーンで不可欠です。
効果的な発信は、誤解を防ぎ、スムーズなコミュニケーションを促し、周囲を動かすための重要な基盤となります。
傾聴力とは
傾聴力とは、単に相手の話を聞くだけでなく、その言葉の裏にある意図や感情、非言語的なメッセージまでを深く理解しようとする力です。
相手が安心して話せる環境を作り、共感を示しながら、注意深く耳を傾けることで、本音や真のニーズを引き出します。
この能力は、顧客の課題を正確に把握したり、チームメンバーの悩みに寄り添ったりする際に極めて重要です。
傾聴を通じて相手との信頼関係を築き、より良い関係性や建設的な解決策へと繋げることができます。
柔軟性とは
柔軟性とは、環境の変化や予期せぬ事態、あるいは異なる意見や価値観に対し、固定観念にとらわれずに適応し、前向きに対応する力です。
計画通りに進まない時や、新たな情報が得られた際に、迅速に考え方や行動を修正し、最適な方法を探る姿勢を指します。
この能力は、技術革新や市場の変化が激しい現代において、ビジネスパーソンに不可欠です。
多様な意見を受け入れ、変化を恐れずに新しいアプローチを試みることで、個人も組織も成長し続けることができます。
状況把握力とは
状況把握力とは、周囲で起きている出来事や、その背景にある要因、さらには将来起こりうる影響までを客観的に認識し、全体像を正確に理解する力です。
目の前の情報だけでなく、複数の情報を統合し、関連性を見出すことで、本質的な状況を読み解きます。
この能力は、プロジェクトの進捗管理、トラブル発生時の初期対応、チーム内の問題発見など、多岐にわたる場面で重要です。
的確な状況把握は、適切な判断を下し、次の行動を決定するための基盤となります。
規律性とは
規律性とは、社会のルールや組織の規則、職場での約束事を理解し、それを遵守して行動する力です。
与えられた役割や責任を認識し、業務プロセスを適切に遂行することで、組織全体の秩序と信頼性を保ちます。
この能力は、コンプライアンスの遵守はもちろん、チームワークを円滑にする上でも不可欠です。
個々が規律を守ることで、予期せぬトラブルを防ぎ、効率的で安全な業務遂行を可能にし、組織としての信用を高めることに繋がります。
ストレスコントロール力とは
ストレスコントロール力とは、仕事や人間関係で生じるストレスを自覚し、それを適切に処理して心身の健康を維持する力です。ストレスの原因を特定し、自身に合った解消法を見つけたり、前向きに気持ちを切り替えたりすることで、パフォーマンスの低下を防ぎます。
この能力は、変化の多い現代社会で長期的に活躍し続けるために極めて重要です。困難な状況でも冷静さを保ち、精神的な安定を維持することで、自身の生産性を高め、周囲にも良い影響を与えることができます。
社会人基礎力が求められる理由
人生100年時代においては、「環境やライフステージに応じて、常に学び続け、自らを振り返りながら、必要なスキルをアップデートしていく」ことが求められています。
常に新しい専門的な知識やスキルを獲得することが不可欠ということです。
一方で、環境が飛躍的・非連続的に変化している現代においては、新たに獲得した知識やスキルが陳腐化してしまうこともあります。
そのため、 「普遍的に求められるスキル」として社会人基礎力がとても重要な役割を果たします。
パソコンやスマートフォンに例えると、社会人基礎力は能力を最大限発揮するためのベースである「OS(オペレーティングシステム)」であると言えます。
仮に新たに獲得したスキルが使えなくなったとしても、社会人基礎力というOSを土台に新たな「アプリ(環境に応じたスキル)」をアップデートしていくことで、環境が大きく変化し続ける中でも活躍し続けることができます。
人生100年時代の社会人基礎力で大切な視点
2018年に経済産業省によって新たに定義された「人生100年時代の社会人基礎力」では、新たに3つの視点が加わりました。
『学ぶ』何を学ぶか
これまでは、「学ぶ⇒働く⇒引退する」という3段階の直線的なキャリアモデルが一般的でした。
しかし、人生100年時代においては、働きながら必要なスキルを積極的に学び、複数のキャリアを持つなど、複線的なキャリアが主流となっていきます。
このような時代の流れをイメージした時に、自分はいったい何を学ぶべきかを考え、常に学び続ける力をつけなければなりません。
自身のキャリアや学びを考えるためにも『考え抜く力』が重要になります。
『統合』どのように学ぶか
何を学ぶかを決めて学びはじめる時には、単に新たなインプットだけで終わらせるのではなく、これまでの体験や培ってきた能力・キャリアと組み合わせて学びを統合させる必要があります。
また、目的の実現に向けて多様な人たちの得意なものと組み合わせていくことも大切です。
『目的』どう活躍するか
これは「自己実現や社会貢献に向けて行動すること」とされています。
どう活躍するかをイメージし、目的を設定した上で「何を学ぶか」「どのように学ぶか」を決めて行動を起こす必要があります。
行動を起こすためには、『前に踏み出す力』が重要です。
社会人チェックシート
自分自身の「社会人基礎力」を具体的に把握し、強みや課題を明確にするために、経済産業省が提供する「社会人基礎力チェックシート」が有効です。
このシートを活用することで、3つの能力と12の能力要素について、現状を客観的に自己点検することが可能です。
これにより、今後の成長に向けた具体的な目標設定や、効果的な能力開発の計画に役立てることができ、キャリア形成を力強くサポートします。
(▼参考・ダウンロードはこちら)
経済産業省:社会人基礎力(人生100年時代の社会人基礎力)
社会人基礎力のおすすめの鍛え方
まずは、社会人基礎力の3つの能力や12の能力要素をもとに、自分ができている点、足りない点を洗い出し、不足しているスキルを把握することから始めましょう。
自分ができていると思っていても、周りからの評価は異なる時もあるので、同僚や上司に客観的な意見をもらうこともおすすめです。
そして、自分に不足している能力が分かったら、高めるためのアクションをとっていきます。
ここでの重要なポイントは、単なる知識の習得ではなく「実践レベル」で鍛えることです。
ビジネススキルを実践レベルで習得するには、やはり書籍や動画学習などの独学などでは限界があります。
もし社内の能力開発環境が不十分であると感じたら、外部の機関で学ぶというのも1つの手です。
例えば、私が勤務しているグロービス経営大学院では、社会人基礎力に該当するスキルを学べる講座が豊富にあります。
その中からいくつかおすすめの講座をご紹介します。
おすすめ①:『クリティカルシンキング』講座
『考え抜く力』を身につけるために適した講座です。
変化の激しい現代では、指示されたことや決められたことをこなすだけでは不十分です。
これからは、「自分の頭で考えて課題を見つけ最適解を導く力」が強く求められています。
「クリティカルシンキング(批判的思考)」はまさに、前提を疑いながら課題の本質を捉えて解決に導くための思考法です。
あらゆる業務をこなすうえでベースとなるスキルなので、積極的に習得していくことをおすすめします。
講座は2週間に一度、計6回の開催。
3ヵ月でかなり思考の仕方が変わりますので、ぜひ検討してみてください。
(▼講座の詳細はこちら)
『クリティカルシンキング』講座
またグロービス経営大学院では、随時オンラインにてクリティカルシンキング講座の『無料体験クラス』を実施しています。
授業の雰囲気や進め方を知りたい方は、まずはこちらからのご参加をおすすめします。
(▼日程一覧はこちら)
おすすめ②:『マーケティング・経営戦略基礎』講座
『前に踏み出す力』を身につけるために適した講座です。
主体性を持って仕事に取り組むためには、自社の存在意義や担当業務の役割をしっかりと理解する必要があります。
社会の中で自社はどういう役割を果たしているのか、会社の中で所属する部署はどのような位置づけなのか、他部署とはどのような関係性なのか、自分の業務はどのような役割を担っているのか。
そうしたことをおさえておくことで、自身のミッションが明確になり、当事者意識を持って仕事に取り組むことができるようになります。
『マーケティング・経営戦略基礎』講座では、会社全体の経営の仕組みや、自社のバリューチェーンがどうなってるのかなど、経営全般の知識を広く学んでいきます。
その結果、より高い視座(=経営者に近い視点)で仕事をみることができるようになり、主体性を持って行動することができるようになります。
(▼講座の詳細はこちら)
『マーケティング・経営戦略』講座
おすすめ③:『組織行動とリーダーシップ』講座
『チームで働く力』を身につけるために適した講座です。
現在、リーダーというポジションでない方でも、組織やチームの一員として協働し成果をあげていくためのマインドを育てるという点で、学びの多い講座です。
ビジネスを取り巻く外部環境が激しく変化する中で、リーダーとして影響力を発揮し、組織を動かすためにどのような行動をとるべきか。
『組織行動とリーダーシップ』講座では、メンバーの力を引き出し、リーダーとして組織で成果を出すための知識を体系的に学びます。
(▼講座の詳細はこちら)
『組織行動とリーダーシップ』講座
おすすめ④:『ファシリテーション&ネゴシエーション』講座
こちらは、『前に踏み出す力』と『チームで働く力』を身につけるために適した講座です。
いくら頭の中に良いアイデアがあっても、それを具体的なアクションプランに落とし込み、実行していかなければ意味がありません。
さらに、ビジネスでは1人で完結する業務は少なく、他者の力が必要な場面が多々あります。
この講座では、周囲に働きかけ、人々を巻き込み、協働していくために必要な考え方とスキルを学びます。
(▼講座の詳細はこちら)
『ファシリテーション&ネゴシエーション』講座
まとめ
社会人基礎力は、学生や新社会人だけでなく、人生100年時代を生きるすべてのビジネスパーソンに必要な普遍的な能力です。
ベーシックであるからこそ、特定の業界や職種などしか使えないスキルではなく、どんな環境にも適応できる汎用性の高い能力です。
新年度を迎えるにあたって、自分自身がどの程度社会人基礎力を備えているのかを今一度見直してみることをおすすめします。
そして、まだ足りていないと思うスキルがあれば、「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「どう活躍するか」を考え、失敗を恐れずに前に踏み出していただけると嬉しく思います。
オンライン体験クラス&説明会日程
著者情報

高原 雄樹(グロービス経営大学院 福岡校 スタッフ)
北九州市立大学法学部卒業。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。楽天株式会社にてインターネットショッピングモール「楽天市場」の出店営業、ECコンサルティング、松山支社の立ち上げ、メンバーのマネジメント等を行う。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院福岡校の成長戦略の立案・実行や組織マネジメント、チームの責任者として従事。キャリアコンサルタント(国家資格)で得た知識・技能をもとに日々学生のキャリアと向き合っている。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。