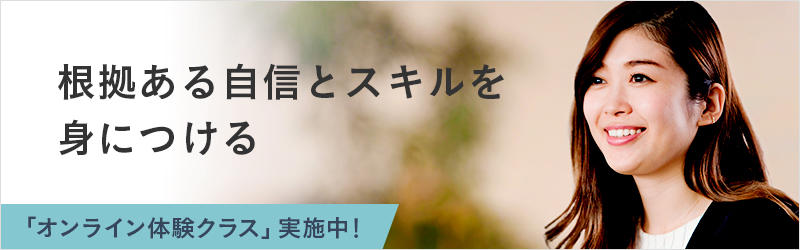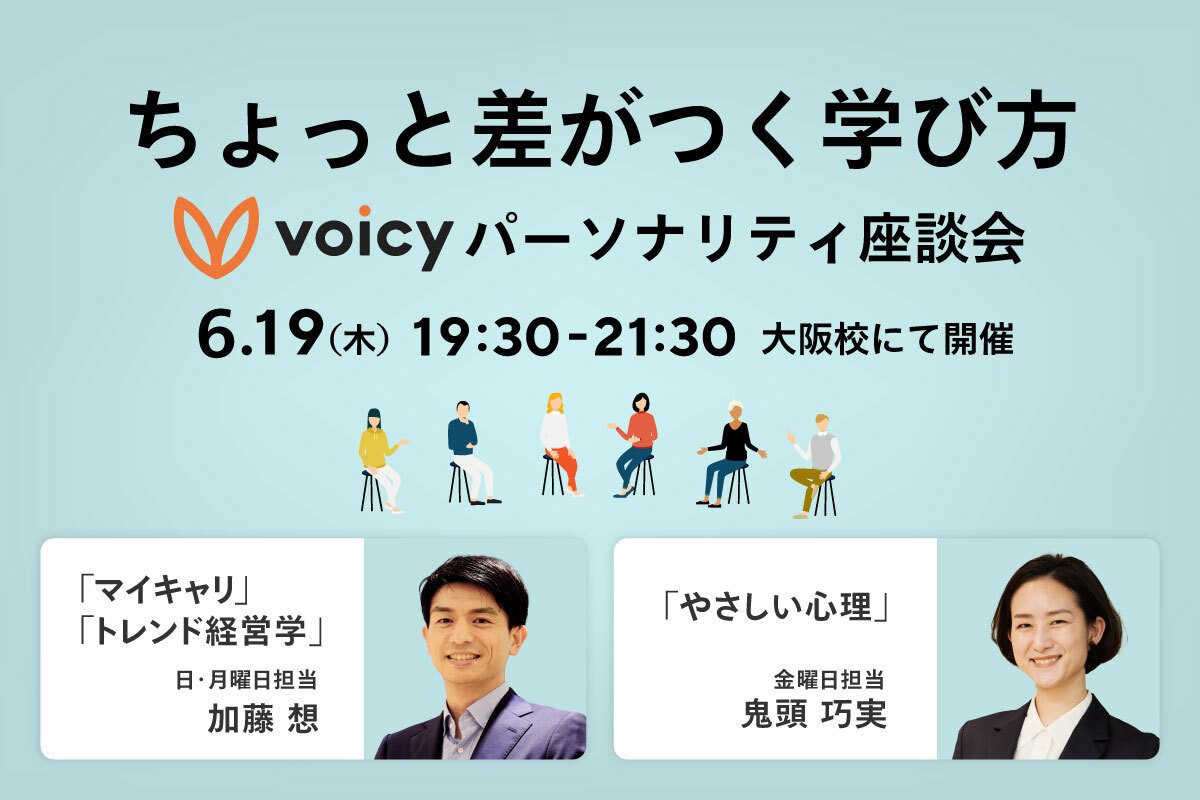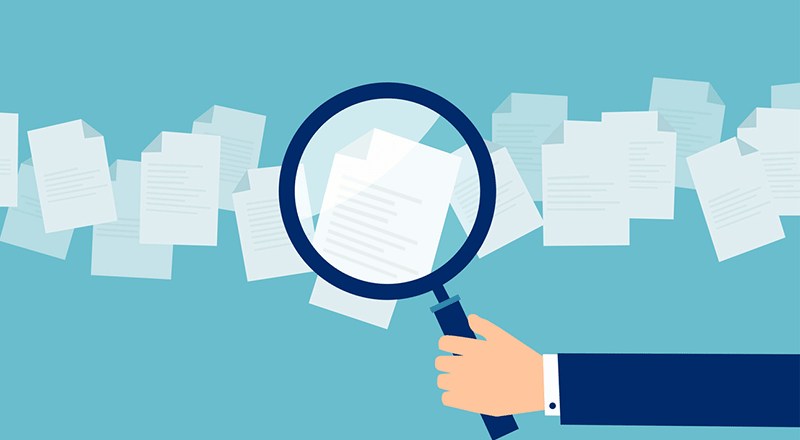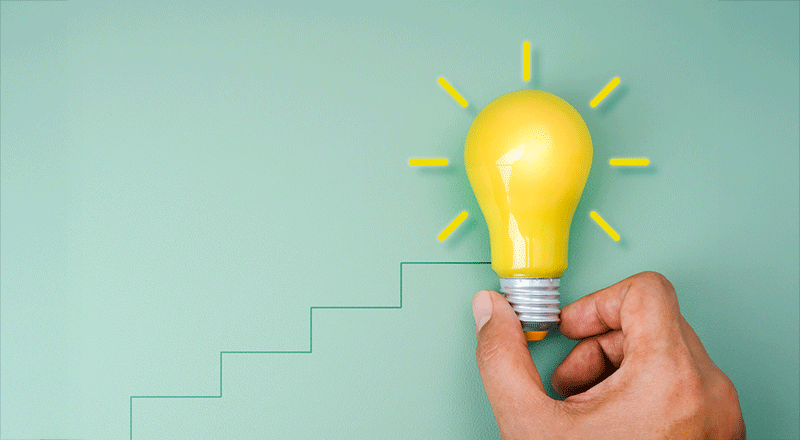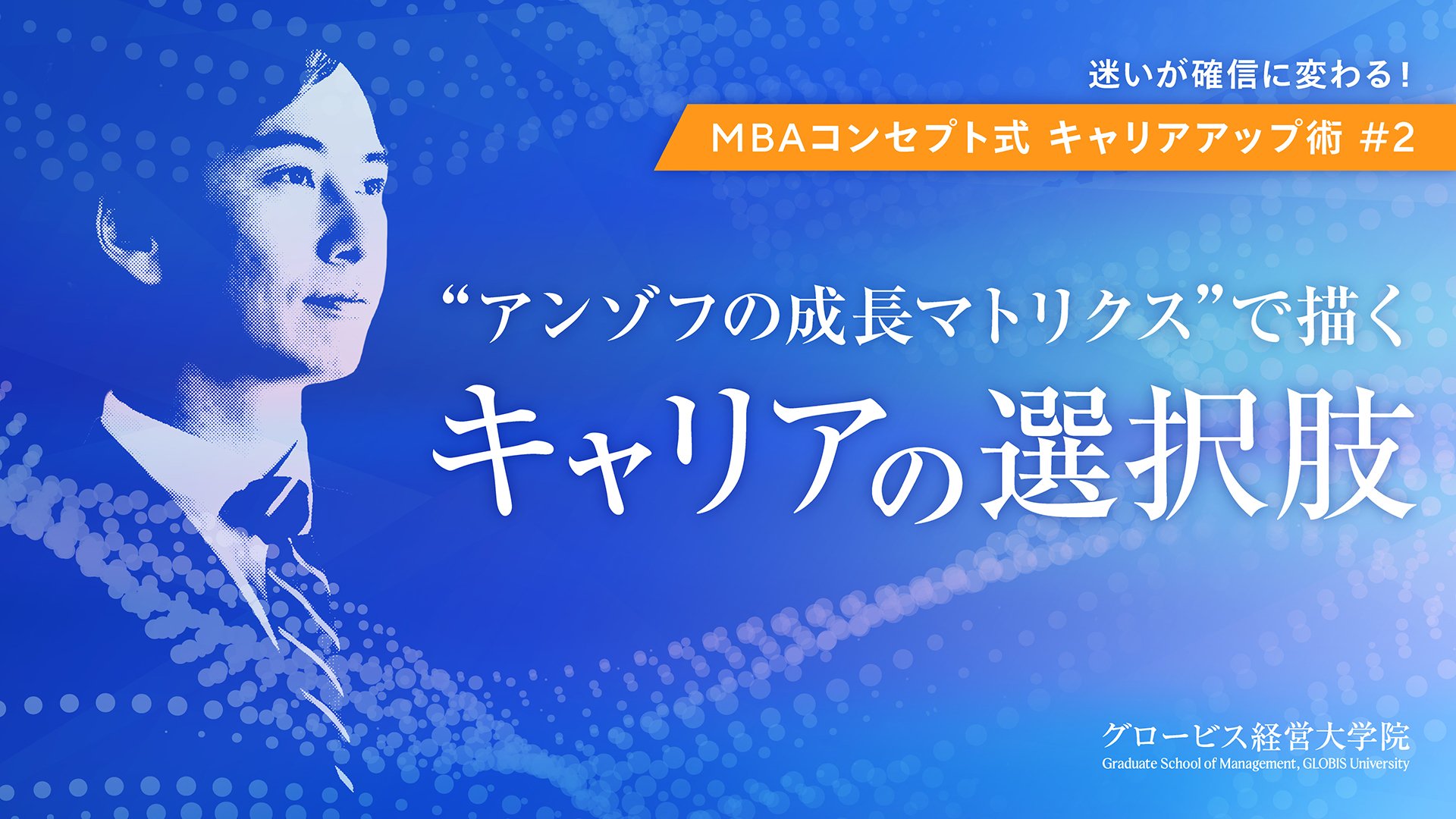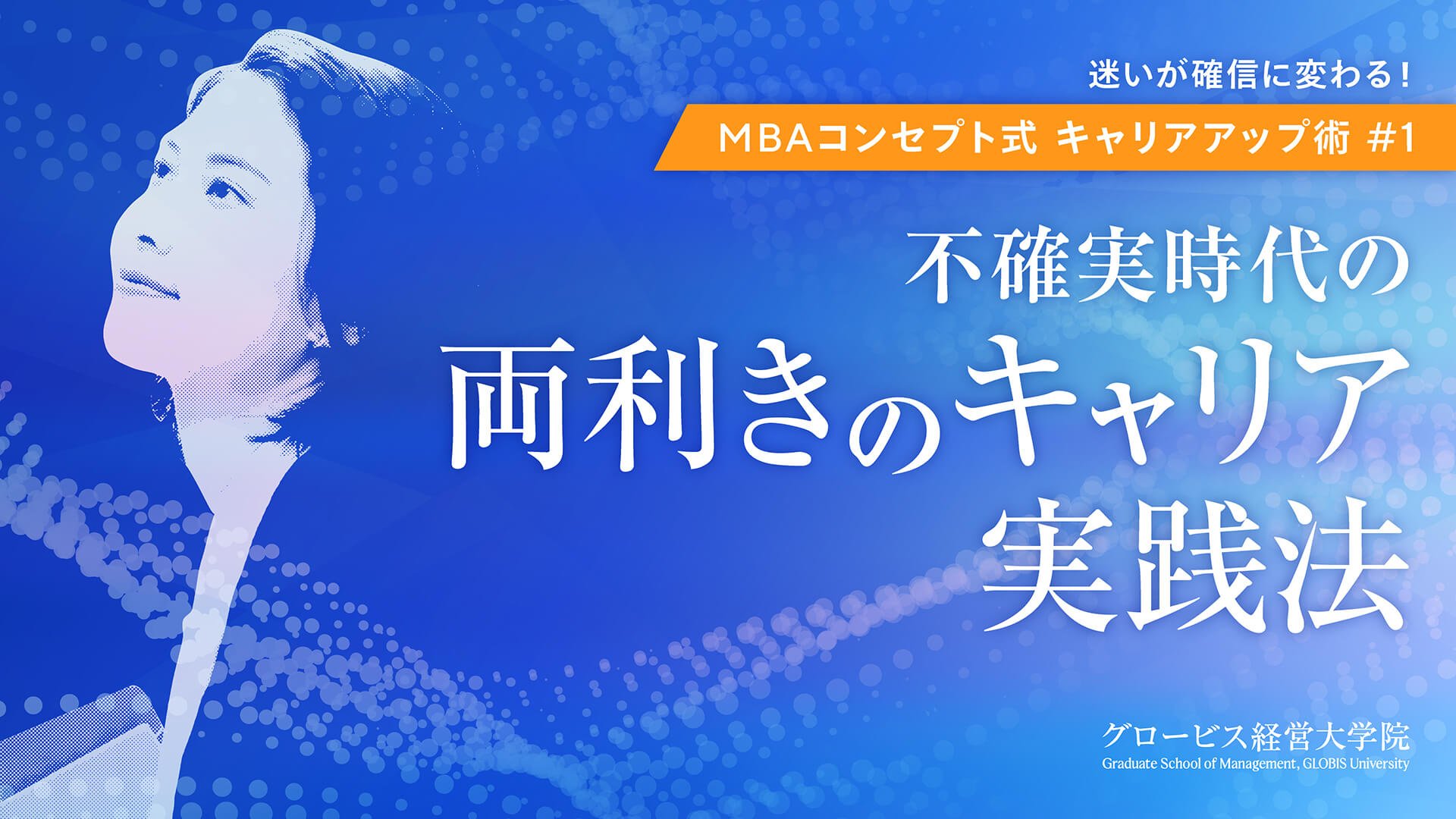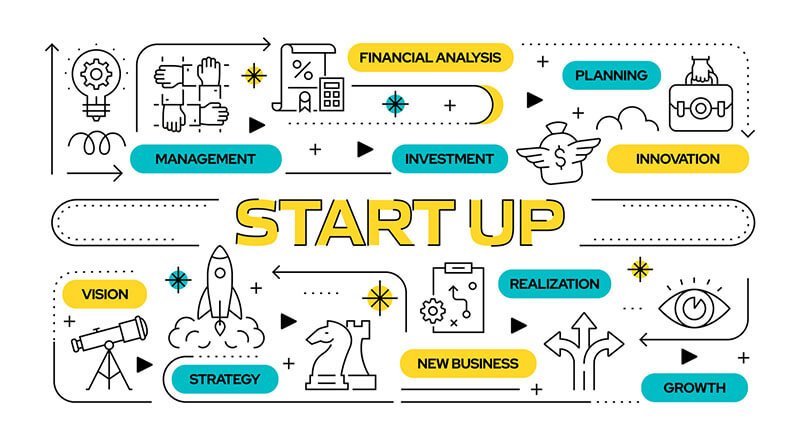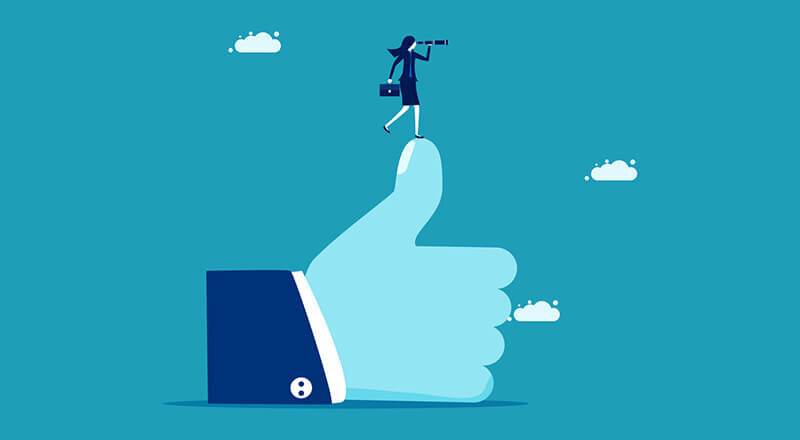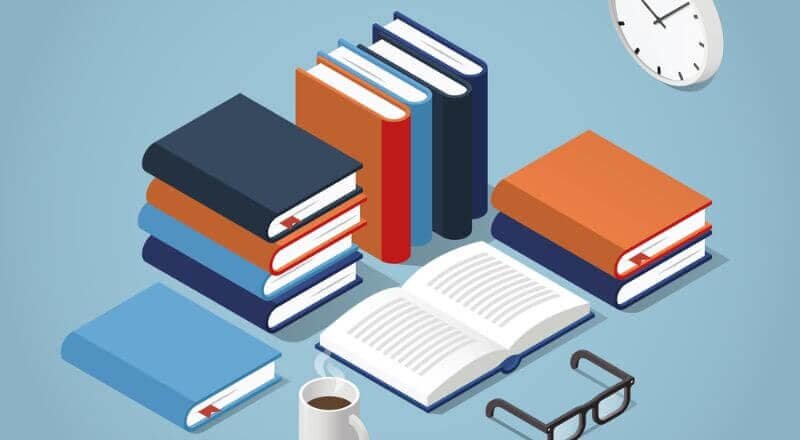目次
AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクス等のテクノロジーの進化、グローバル化の進展など、社会環境がめまぐるしく変わり続ける現代。加えて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済活動のさまざまな場面で制約がかかる中、私たちビジネスパーソンは常に大きなストレスにさらされています。
しかし、同じストレス下で働いていても心が折れる人と折れない人がいます。 複雑化する社会環境の変化に適応する力として近年注目されているのが「レジリエンス」です。本記事では、折れない心をつくるためのキーとなる「レジリエンス」の高め方についてご紹介します。
レジリエンスとは
レジリエンスとは、回復力・復元力などの自発的治癒力を表す言葉です。もともとは心理学の世界で困難や脅威に直面した時に「うまく適応できる能力」「うまく適応する過程」「適応した結果」を意味する言葉として使われてきました。現在ではビジネスにおいても、逆境や困難を乗り越える力として注目されています。
レジリエンスという言葉は、ラテン語の「resilire(跳ね返る)」が語源とされています。近年、子どもの発達心理学の分野で注目され始め、困難な状況にあっても精神的健康を維持できる能力として研究されてきました。心理学においては、ストレスや困難に直面しても心理的安定を保ち、それを乗り越えて成長する力を指します。
一方、ビジネスの文脈では、変化や予期せぬ危機に対して柔軟に対応し、迅速に回復する組織や個人の能力として捉えられています。近年の不確実性の高いビジネス環境において、このレジリエンスを高めることが、持続的な成功の鍵として重視されるようになっています。
レジリエンスが重要視されている背景
急速な社会変化への対応
レジリエンスがビジネスの現場でも注目を集めるようになった最大の背景は、時代の変化が加速度的に速くなってきたことが挙げられます。企業やそこで働くビジネスパーソンは今、テクノロジーの進化やグローバル化の進展など、急激な環境変化に適応していかなければなりません。
また、DXの波により、従来のビジネスモデルが短期間で陳腐化するリスクが高まっています。さらに、AIや自動化技術の発達により、これまで人間が担ってきた業務の多くが機械に置き換わる可能性が指摘されており、ビジネスパーソンには新たなスキルセットの習得が求められています。
働き方の多様化と複雑化
もう一つの重要な背景として、労働環境の大きな変化が挙げられます。テクノロジーが進化したこととコロナ禍によって、オフィスに出社せずに業務を行うリモートワークが増え、ジョブ型の働き方が広がっています。
また、終身雇用の概念がなくなり、人材の流動性も高まりつつあります。これにより、従来の安定した雇用環境とは異なる、より不確実で変化に富んだ働き方が一般的になってきました。このような環境下では、予期せぬ変化や困難に直面しても、迅速に立ち直り、新たな状況に適応する能力が不可欠となっています。
煉獄さんのセリフが変化の時代におけるキーに
「鬼滅の刃」という、私の大好きな漫画の登場人物のセリフにこのような言葉があります。
「己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯をくいしばって前を向け。君が足をとめてうずくまっても時間の流れはとまってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない」
レジリエンスを考える上で、この言葉は核心をついていると感じます。変化の激しい時代。仕事で困難な場面に直面することが多くなっています。時間の流れはとまってはくれません。仕事の重圧に押しつぶされそうになったり、失敗したりすることもあるかもしれません。しかし、それでも心を燃やしてまたチャレンジするために「レジリエンス」を高めておきたいものです。
レジリエンスの因子とは?どのように評価する?
レジリエンスの因子とは
レジリエンスの因子とは、個人や組織の回復力を左右するさまざまな要素のことを指します。これらの因子は、ストレスや困難に直面した際の対処能力に大きく影響を与えます。
レジリエンス研究において、因子は主に「危険因子」と「保護因子」の2つのカテゴリーに分類されます。この考え方は、個人がストレスフルな状況に置かれた際に、どのような要素が悪影響を与え(危険因子)、どのような要素が回復を促進するか(保護因子)を体系的に理解するために開発されました。
危険因子
危険因子とは、心の回復を妨げて、ストレスや困難に対処しにくくする要素のことです。
まず個人においては、長引く体調不良や「自分にはできない」という思い込みが大きく影響します。いつも悪い方に考えてしまう人や、人とのコミュニケーションが苦手な人、何でも完璧にやろうとしすぎる人は、困った時にうまく対処できなくなりがちです。
次に環境面では、お金の心配や周りに相談相手がいないことが代表的な問題です。職場でのいじめや嫌がらせ、家族との関係悪化なども、心の回復力を大きく下げてしまいます。これらの問題は一人では解決が難しいため、周りの人や専門機関の助けが必要になることが多いです。
保護因子
保護因子とは、困難な状況でも心の回復を助けてくれる要素のことです。
まず個人の能力として、「自分ならできる」という自信と、物事をさまざまな角度から考える柔軟性が重要です。問題を解決する力や感情をコントロールする力、前向きに物事を捉える力も、困難を乗り越える大きな助けとなります。
次に人間関係では、家族や恋人、信頼できる友人の存在が基盤となります。職場の同僚や先輩との良好な関係も大切です。困った時に相談できる相手がいることで、一人で抱え込まずに済みます。
最後に環境面では、安定した仕事があることや学習機会に恵まれていることが挙げられます。安全な住環境や地域の支援体制も、困難に立ち向かう際の重要な支えとなります。
レジリエンス因子を評価する指標
レジリエンス因子の評価には、さまざまな測定尺度や指標が開発されています。
最も広く使用されているのが「Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)」です。この尺度は25項目からなる自己評価式の測定ツールで、「困難を成長のチャンスと思えるか」「変化にうまく対応できるか」「目標に向かって諦めずに頑張れるか」など、さまざまな角度からレジリエンスを測ることができます。
より簡便な測定方法として「Brief Resilience Scale(BRS)」があります。6項目で構成されており、困難からの回復能力に焦点を当てて測定します。短時間でできるので、会社で定期的にチェックしたり、研修の効果を確認したりするのに便利です。
個人だけでなく、会社全体の回復力を測る方法もあります。会社の文化がどれだけ浸透しているか、リーダーの質はどうか、コミュニケーションはうまくいっているかなどを調べて、その組織が困難にどれだけ対応できるかを客観的に知ることができます。
レジリエンスと類語との違い
メンタルヘルスとの違い
メンタルヘルスは、精神的健康状態そのものを指すのに対し、レジリエンスは困難や逆境から回復する動的な能力を意味します。メンタルヘルスが現在の心の状態を表すのに対して、レジリエンスは変化や困難に対する適応プロセスに焦点を当てています。
つまり、メンタルヘルスが良好であることとレジリエンスが高いことは必ずしも同義ではありません。現在精神的に安定していても、突然の変化に対する適応力が低い場合もあれば、一時的に落ち込んでいても迅速に回復する力を持っている場合もあります。
ストレス耐性との違い
ストレス耐性は、ストレスを受け流すまたは耐える能力を指すのに対し、レジリエンスは困難な状況を乗り越えて成長する能力を含みます。ストレス耐性は防御的な概念であるのに対し、レジリエンスはより積極的で変革的な概念です。
高いストレス耐性を持つ人は困難な状況でも動じないかもしれませんが、レジリエンスの高い人はその困難を学習と成長の機会として活用し、以前よりも強くなって立ち上がることができます。
適応力との違い
適応力は環境の変化に合わせる能力を指すのに対し、レジリエンスは困難な状況を変えるまたは活用する能力も含みます。適応力は主に環境に対する受動的な調整を意味しますが、レジリエンスはより能動的で創造的なアプローチを伴います。
適応力の高い人は新しい環境に素早く馴染むことができますが、レジリエンスの高い人はその環境をより良いものに変革したり、困難な状況から新たな価値を創造したりすることができます。
忍耐力との違い
忍耐力は困難な状況を我慢して耐え抜く能力を指すのに対し、レジリエンスは困難な状況を積極的に克服し、そこから学ぶ能力を意味します。忍耐力は静的で消極的な概念であるのに対し、レジリエンスは動的で積極的な概念です。
忍耐力の高い人は長期間にわたって困難に耐えることができますが、レジリエンスの高い人はその困難を乗り越える具体的な方法を見つけ出し、将来の類似した困難により良く対処できるようになります。
レジリエントな人(心の回復力がある人)の特徴
レジリエンスがある人は逆境に遭遇してもうまく乗り越えることができます。レジリエントな人はどんな特徴を持っているのか、主に3つご紹介します。
柔軟で多面的な思考力を持ち、目の前の状況に一喜一憂しない
レジリエントな人は、柔軟かつ多面的に物事を捉えるため、一面では悪いと思えるような出来事でも、あらゆる側面から考えることによってポジティブに解釈し最適なアクションを見いだします。そのため、目の前の出来事に一喜一憂することなく感情が常に安定しています。
周囲との信頼関係を築くことが得意
柔軟かつ多面的な思考をすることから、周囲から様々な意見を集めることができます。一方的なコミュニケーションではないため、周囲との信頼をうまく構築していきます。その信頼をベースにして、自分にできない範囲の仕事は周囲に任せたり、頼ったりすることができます。
困難や失敗があってもチャレンジし続ける
困難なことがあったり失敗したりすると、次の挑戦が怖くなることは珍しいことではありません。しかし、レジリエントな人は、困難や失敗があっても「次はどうすればよいか」「他にできることはなかったか」など多面的に捉え、そこから学び成長しようとします。物事をポジティブに捉え、次のチャレンジに結びつけていくことができます。
個人がレジリエンスを高めるメリット
レジリエンスを高めることは個人にとっても企業にとっても大きなメリットがあります。
ストレス耐性が身に付く
高いパフォーマンスを発揮する上で、ストレスが全くないほうがよいかというとそうではなく、適度な緊張感は重要な要素です。しかし、過度にストレスを感じるとパフォーマンスに悪影響を及ぼしたり、体調不良に陥ったりする恐れがあります。 レジリエンスを高めておくことで、ストレスを受けても回復し立ち直ることができるようになります。
また、ストレスをうまく受け流せるようになったり、ストレスをエネルギーに変換したりする力も身につきます。ストレスと適切に向き合うことで、精力的に業務に取り組むことができます。
変化への適応力が身に付く
社会が急激に変化することに伴い、転勤や出向、リモートワークの導入など働く環境も大きく変化しています。
また、企業合併(M&A)の数が年々増えています。
M&Aともなると別の会社に転職したように組織文化がガラッと変わります。
レジリエンスを高めておくことで、このようなめまぐるしい環境変化にも柔軟に適応することができます。
目標達成能力が身に付く
社会環境の変化により顧客のニーズが多様化していることもあり、目標達成することが難しくなっています。多くの場合、なかなか思いどおり進捗せず、大きなストレスと向き合わなければなりません。
レジリエンスを高めておくことで、目標達成のストレスに適切に対応することができます。困難な場面でも折れない心があれば、たとえ失敗したとしても乗り越えて活動を続けることができます。
企業にとってレジリエンスを高めるメリット
企業が社員のレジリエンスを高めることには、大きなメリットがあります。
離職率を下げ、社員が活き活きと仕事をするようになる
組織のレジリエンスが高まると、仕事のストレスと適切に向き合うことできる社員が増え、ストレスで体調を崩して離職してしまう社員を減らすことができます。レジリエンスの高い社員はストレスを適度な緊張感として前向きにとらえ、活き活きと仕事に取り組んでくれます。
組織にダイバーシティが生まれる
日本の労働人口が減少する中、女性活躍および幅広い年齢の活躍、外国人雇用などダイバーシティ・マネジメントに取り組むことは企業にとって重要なテーマです。 組織のレジリエンスを高めることで、年齢的・性的多様性を認め、国や人種によって異なる価値観を受け入れる組織風土をつくることができます。
戦略転換やリスクにも臨機応変に対応できる
社会環境の変化に伴って戦略を転換しなければならないケースは、今後ますます増えていくでしょう。また、想定外のリスクや困難な事態に陥ることもあります。組織のレジリエンスを高めることで、戦略転換や困難なリスク課題に直面しても、レジリエントな社員の能力によって乗り越えることが期待できます。
外部から企業を評価する指標となる
近年、企業のレジリエンスは外部からの評価指標としても重要視されています。投資家や顧客、求職者は、企業が困難な状況にどのように対処し、回復する能力を持っているかを評価の基準として考慮するようになっています。
レジリエンスを高める方法
レジリエンスの高低には、ある程度の遺伝的要素があると言われていますが、誰もが多かれ少なかれ内面に持っている特徴でもあり、後天的に高めていくことができます。そこで、レジリエンスを高めるための方法を3つご紹介します。
自己効力感を高める
自己効力感とは、困難な出来事に対して、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認知状態のことです。自ら困難な目標に挑戦し、チャンスを生み出していくことができます。
自己効力感の高め方については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ合わせて読んでみてください。
思考パターンを変える
多くの人が「思考を変えるのは難しい」と思うかもしれませんが、正しいやり方を理解し、実践することで思考は変えることができます。そこで、臨床心理学の博士アルバート・エリスが提唱した、「ABCDE理論」という論理療法をご紹介します。
・A(Activating Event)=出来事、事実
・B(Belief)=信念(考え方、価値観、思い込み)
・C(Consequence)=結果(解釈により生じる感情や行動、身体反応)
人は、出来事や事実(A)に対して、自らが持っている信念(B)によって解釈し、その結果として感情や行動・身体反応(C)が引き起こされます。 具体的にみていきましょう。
A:出来事
職場で上司に怒られた。
B:考え方
上司の期待に応えることができず、仕事ができないと思われてしまったに違いない。
C:感情
自分は何をやってもうまくいかない。
ある出来事に対してこのように捉えてしまうことがあるかもしれません。この時、「ABCDE理論」では、Bの考え方が果たして正しいのか、自ら反論を加えてみます。
・D(Dispute)=反論(自分の捉え方への疑問・反論)
自分の考え方(B)を自覚し、反論してみることで結果として捉え方が変化して、より好ましい捉え方をすることができます。
先ほどの具体例でいうと、「上司は期待してくれているからこそ指摘をしてくれた(B)」という新たな捉え方をしてみると、「今回の指摘を反省点にして次回同じようなミスをしないようにしよう(C)」という感情に変化させることができます。修正した捉え方によって得られる影響を効果(Effect)と言います。
・E(Effect)=効果(効果的な新しい信念体系や人生哲学)
このように、Aという出来事や事実は変えられなくても、Bの信念に反論を加えてみて好ましい捉え方、解釈をすることで思考パターンを変えることができます。ABCDE理論の考え方を日常生活のなかで取り入れてみると、レジリエンスが高まり、物事を多面的に捉えポジティブに解釈できるようになります。
周囲とのつながりを持ち、サポートを得る
困難に直面した時、どうしても一人ではポジティブに捉えることができない 場面も出てくるかもしれません。そんな時、一人で抱え込まずに周囲に共感、サポートしてもらえる関係性をつくっておくことも非常に大切です。
まずは、自ら周りをサポートすることで、周囲からの信頼を築いておくといいでしょう。多くの人は、「人から何かしてもらったら、お返しをしてあげたい」という返報性の原理が働くものです。 何より、一人でできることには限界があります。
周囲と協力をすることでより複雑で困難な問題にもチャレンジすることができるようになります。それは、個人のレジリエンスを高めるだけでなく、組織としてのレジリエンスを高めることにも繋がります。
チームのレジリエンスを高める方法
個人のレジリエンスだけでなく、チームのレジリエンスを高めるための方法を2つご紹介します。
企業文化の醸成、独自性の追求
企業が何のために存在し、 社会にどのような価値を提供するのかという存在意義(ビジョン・ミッション)を明確にし、社員の普段の行動レベルに根付かせておくことが重要です。社員の行動の集合体が企業文化となり、環境変化にあわせてチーム一丸となって動く土台ができあがります。
そして、他社にはない自社の「独自性」を磨いておくことで、環境や市場のニーズの変化に柔軟に対応できる武器となりチームのレジリエンスが高まります。
心理的安全性の高い職場づくり
個人が困難や失敗から回復しようとする時、組織がそもそも失敗を許容しない文化だと、レジリエンスを発揮することができません。ミスした時でもその失敗を隠すことなく素直に打ち明けることができ、それが許容され、次にどうすればいいかの解決策を一緒に考えることのできる組織だと、個人のレジリエンスが促進されていきます。
心理的安全性の高い職場は、メンバー一人ひとりがチームに対して気兼ねなく発言でき、周囲を過度に気にせず挑戦・行動できる職場環境・雰囲気があります。
「失敗するくらいなら挑戦しないほうがよい」と思わせるのではなく、「失敗を奨励する風土」「失敗から学び次に生かすことができる組織」にすることで、心理的安全性の高い職場になります。心理的安全性の高い職場では、困難な課題に直面してもチャレンジする社員が増え、チームのレジリエンスが高まります。
逆境に負けないコミュニケーション力を実践で学ぶ
レジリエンスの向上には、他者との良好な関係性を築き、困難な状況でも適切にコミュニケーションを取る能力が欠かせません。ビジネスコミュニケーション能力を向上させるには、外部の教育機関を活用するのもひとつの方法です。
例えば、グロービス経営大学院ではコミュニケーションの基盤となる思考力から実践的なスキルまで学べるカリキュラムを提供しています。「クリティカル・シンキング」では論理的思考の基礎を固め、困難な状況を客観的に分析し最適な解決策を導く力を養うことができます。
日々の実践に加えて、このような専門的な学びの場を活用することも検討してみるとよいでしょう。
まとめ
今回は「レジリエンス」について、ビジネスで求められている背景やレジリエンスを高めるメリット、高めるための方法についてご紹介しました。 皆さん自身が個人でレジリエンスを高めたいと思った時、またはチームとしてレジリエンスを高めたいと思った時、本記事が少しでもお役立ちできると大変嬉しく思います。
また、レジリエンスを身に付けるには、逆境に直面した際に状況を冷静に分析し、最適な解決策を導き出す「考え抜く力」が欠かせません。この考え抜く力を効果的に育成するのが「クリティカル・シンキング」です。具体的な内容をより詳しく知りたい方は、グロービス経営大学院の体験クラスに参加することで、実際の授業の雰囲気や学びの深さを体感することができます。
著者情報

高原 雄樹(グロービス経営大学院 福岡校 スタッフ)
北九州市立大学法学部卒業。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。楽天株式会社にてインターネットショッピングモール「楽天市場」の出店営業、ECコンサルティング、松山支社の立ち上げ、メンバーのマネジメント等を行う。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院福岡校の成長戦略の立案・実行や組織マネジメント、チームの責任者として従事。キャリアコンサルタント(国家資格)で得た知識・技能をもとに日々学生のキャリアと向き合っている。
※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。